研修旅行は、1968年の青山学院大学史学科の創立以来、他大学にはみられない特色ある授業として、3年次の全員が参加して毎年行っている伝統行事です。史料の読解や解釈を行う「デスクワーク」と、歴史的な出来事の現場に実際に赴いて調査する「フィールドワーク」の両方を通じて歴史をバランスよく学ぶことが、本学史学科の創立以来の理想となっています。(画像は研修旅行先の一つである沖縄県・今帰仁城跡)
史学科
DEPARTMENT OF HISTORY
AOYAMA CAMPUS
歴史に秘められたロマンとダイナミズムにふれ、
より良い未来を築く洞察力を養おう
- MENU -
MOVIES 動画で知る史学科
NEWS・EVENT 史学科のニュース・イベント
-

NEWS
2024.9.19FOCUS: Race to find next Japan PM may prove ruling party factions die hard
-

NEWS
2024.7.26【史学科】後藤里菜准教授の新刊書『沈黙の中世史』(ちくま新書)が刊行
-

NEWS
2024.7.22史学科の谷口雄太先生が編著者をつとめた『足利一門と動乱の東海(東海の中世史2)』(吉川弘文館)が刊行されました。
-

EVENT
2024.7.1【史学科】日本文化財科学会第41回大会
-

NEWS
2024.6.12【文学研究科】市川周佑さん(史学専攻 博士後期課程3年)が「石橋湛山新人賞」を受賞
-
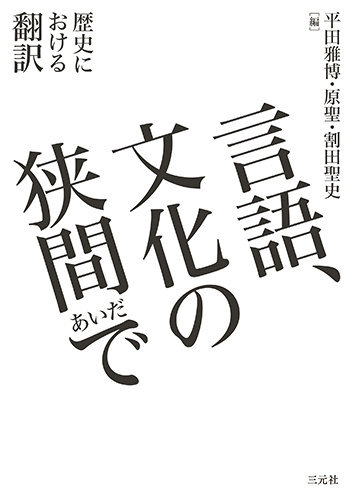
NEWS
2024.4.14【文学部 史学科】安村直己先生と割田聖史先生が寄稿した『言語、文化の狭間(あいだ)で―歴史における翻訳―』(三元社)が刊行
FEATURES 学科の特色
-
「読み解く歴史」を学ぶ
大学で学ぶ歴史学は、中学校や高校で勉強してきた日本史や世界史とは大きく異なります。年号や名称をひたすら覚える「暗記もの」ではなく、自ら史料を紐解き、主体的に歴史を考え、真実を探る、「読み解く歴史」を学ぶのです。
-
従来の枠組みを踏まえつつ、乗り越える
日本史、東洋史、西洋史、考古学という従来の歴史学の枠組みを大事にしながら、それを越えたより広い視点で、過去の事象にアプローチします。歴史は、異なる文化が複雑に関連しながら展開していくものだからです。
-
教員の充実と多彩な顔ぶれ
豊富なカリキュラムに対応すべく、16 名の専任教員と、約40 名にのぼる非常勤講師が授業を担当します。教員の充実は、他大学に例を見ない、本学の特色のひとつです。
-
フィールドワークで確かめる歴史の現場
歴史をより広く深く学ぶためには、史料を読み解き考えたことを現地に出向いて確かめるフィールドワークが欠かせません。そのため史学科では、各ゼミを主体とする研修旅行を3年次に実施しています。知っているつもりの出来事がなぜそうなったのか、歴史の現場でさらに探究してみましょう。
PICK UP LECTURES 授業等紹介
考古学実習Ⅰ・Ⅱ
考古学は発掘されたモノから人々の歴史を復原する学問です。実習では発掘調査や遺物の整理作業を通して、学問の基礎を実践的に学びます。2015年度からは、秋田県横手市教育委員会と連携し、後三年合戦の遺跡と推定される金沢城跡等で調査を行っています。
感染症アーカイブズ(AIDH)
「感染症アーカイブズ(AIDH)」は、感染症や寄生虫病、また風土病などの疾病に関するさまざまな資料を収集・整理・保存・公開する試みです。さまざまな講演会・セミナー・ワークショップなども国内外で開催しています。詳しくはこちらをクリックしてください。
史学会公認研究会
有志が集まって歴史に関する研究会を結成しています。活動内容は史料や研究の輪読・博物館見学などで、現在、考古学や日本近代史、西洋中世史ほか、10の研究会が活動中。写真は食文化史研究会の調理実習で、2種類のカレーを作った時のものです。
PICK UP SEMINARS ゼミナール紹介
日本近世史ゼミ(岩田みゆき)
日本近世史・幕末社会史の研究、特に江戸時代の村や町に残された史料の解読と研究を行います。古文書の基礎知識を学ぶとともに読解力を養います。また各自それぞれの関心に基づいたテーマをみつけて報告をしてもらいます。
南アジア史、アジア各地史ゼミ(二宮文子)
教員の専門は南アジア史ですが、ゼミでは南アジア、西アジア、中央アジア、東南アジアなどを対象としています。使用言語面で厳しい分野ではありますが、興味がある分野の史料(の翻訳)を卒業論文で用いることを目標にしています。
ヨーロッパ近現代史ゼミ(割田聖史)
「今自分たちの世界がどこにあり、どこに行こうとしているのか」。このようなことを考えることはありませんか。歴史学は、過去の事跡を暗記するだけの学問ではありません。歴史学とは、過去を考えることで、今・ここにいる私たちを探る学問であり、このような問いを考えるときにもきっと役に立つ学問です。ゼミでの文献講読と議論、各自の卒論執筆を通じて、今・ここにいる自分たちの位置を一緒に考えていきましょう。
考古科学ゼミ(菅頭明日香)
考古学の遺跡や遺物について、自然科学的な手法を用いて研究を行っています。考古科学は、年代・産地・古環境など、考古学における様々な課題に貢献できます。遺跡や遺物を分析し、ただ数値をみるのではなく、遺跡や遺物を壊さないために分析方法を改良工夫し、分析結果と歴史的背景がどう結びつくのか、自ら考えていくことを大切にしたいと思います。
INTERVIEW 在学生・卒業生インタビュー
-
 平田 さくら 在学生
平田 さくら 在学生<2022年度 学業成績優秀者表彰 優秀賞受賞>
「過去に学び、本質を見極め、継承する」姿勢と「好き」をつなげて未来を切り拓く平田 さくら 在学生 -
 森野 裕成 在学生
森野 裕成 在学生<2023年度 学業成績優秀者表彰 奨励賞受賞>
細かい検証から事実を探る歴史学に魅了され、計画性をもって剣道と勉学の文武両道を実現
(2023/8/24公開)
森野 裕成 在学生 -
 瀬戸口 薫 在学生
瀬戸口 薫 在学生<2022年度 学友会表彰(体育会表彰)最優秀選手受賞>
大空を舞台にグライダーで滑翔する楽しさとチームの大切さを知った体育会航空部
(2023/6/8 公開)瀬戸口 薫 在学生 -
 森 就 在学生
森 就 在学生ゼロから学んだ歴史学。数多くの文献や議論を通してその重要性に目覚めた
(2023/02/28 公開)森 就 在学生 -
 CHOI JIIN (チェ ジイン) 在学生
CHOI JIIN (チェ ジイン) 在学生歴史の客観的な学びには幅広い視野が不可欠
(2022/08/12 公開)CHOI JIIN (チェ ジイン) 在学生 -
 王 赫・黄 溢哲 在学生
王 赫・黄 溢哲 在学生<2022年度学業成績優秀者表彰>
青学で出会った留学生二人の、向学心を支える学びの環境
(2022/7/29 公開)王 赫・黄 溢哲 在学生 -
 大杉 耀歩 在学生
大杉 耀歩 在学生多様な分野の中で培った多角的視点そしてさらなる歴史の探究へ
(2021/10/26 公開)大杉 耀歩 在学生 -
 田﨑 祥子 在学生
田﨑 祥子 在学生<フラサークル「Uluwehi(ウルヴェヒ)」>
サークル創設後に待っていた仲間との宝物のような日々
(2021/2/5 公開)田﨑 祥子 在学生
INTERVIEW 教員インタビュー
-
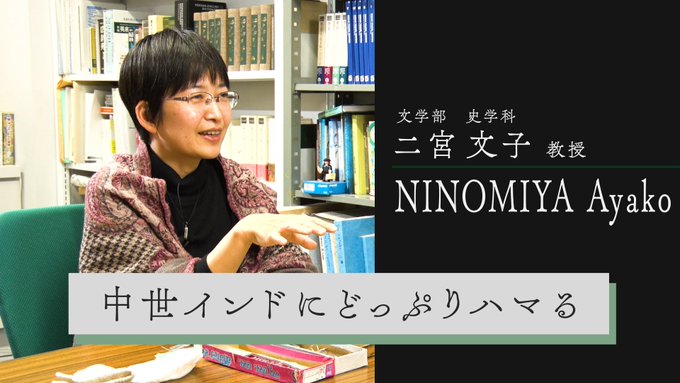 二宮 文子 教授 アオ・ガク・モン
二宮 文子 教授 アオ・ガク・モン中世インドにどっぷりハマる
(2022/3/4 公開)二宮 文子 教授 アオ・ガク・モン -
 稲垣 春樹 准教授・伊藤 真子 ゼミインタビュー
稲垣 春樹 准教授・伊藤 真子 ゼミインタビューイギリス近現代史を通して、自分と異なる他者に向き合う
(2021/12/14 公開)稲垣 春樹 准教授・伊藤 真子 ゼミインタビュー