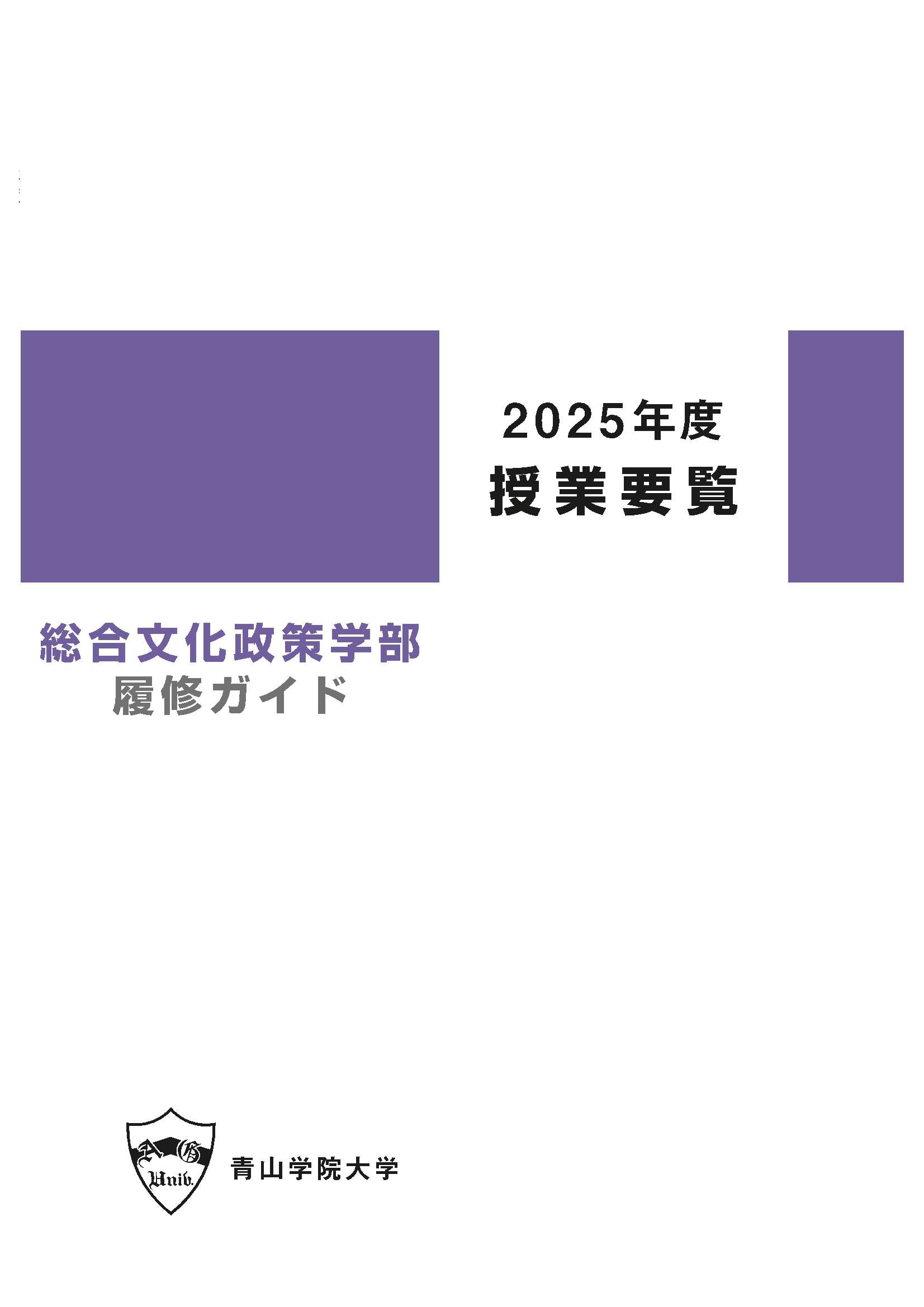- 2025年度 授業要覧 総合文化政策学部
学びの特色とカリキュラム(総合文化政策学科)
※ここで紹介する履修モデルは、あくまでも一例です。
COURSE FEATURES 主要科目の特長
人文系科目
| 科目名 | 特長 |
|---|---|
|
文化産業概論
|
エンタテイメント、メディアを含む「デジタルコンテンツ産業」が文化政策上重要性を増している経済的背景を探り、これらの産業が現在進みつつある環境変化を理解し、今後の課題を検討する。
|
|
芸術文化政策論
|
世界の主要国の文化政策とは何かを理解し、基本的知識を身につけた上で、特に文化と産業、文化と都市開発の関係を追求し、さらに文化とメディアや文化とテクノロジーとの関係を探求する。
|
|
メディア・コミュニケーション論
|
政治から経済、文化に至るまで、世界には様々な出来事や課題が存在しますが、メディアを通じて社会に流通する紋切り型のイメージをそのまま受け容れるのではなく、それらをつねに吟味し、さまざまな情報源にあたり、複数の眼差しを投じてほしいと思います。この姿勢のもと、ささやかであれ、自ら感じ取り、調べ、考え、書く空間を、教室にて一緒に創り出していきましょう。歴史に学びながら、現代のメディアとコミュニケーションについて探究します。
|
|
表象文化概論
|
文化を分析するには、いろいろなアプローチがあり得るだろう。この授業は、とくに文化における「芸術表象」の重層的なありかたに注目するのが特徴である。教室では、さまざまなジャンルからもっとも重要なテキストを選んで検討していくことにしている。
|
|
多文化共生論
|
異なる文化を理解し共生を目指すためには、文化の基底にある世界観、とくに生命観の成り立ちを解読する必要がある。この講義では、人間が生命をどのように捉えてきたかを総合的な視点から考えなおすことを目的とする。
|
|
祭祀文化論
|
「祭り」と聞いて何を想像するだろう?神輿や屋台、華麗な山車……。では、神輿とはなんだろう?なぜ特別な衣装に身を包み、特別なごちそうを食べるのだろう?日本各地のさまざまな祭りの身近な不思議に迫りつつ、日本人の心を探る。
|
社会系科目
| 科目名 | 特長 |
|---|---|
|
都市計画論
|
都市はどのような活動から生まれるのか、その都市活動は都市の良さと同時にどんな問題を引き起こすのか、その解決のためにどのような都市計画制度ができたのかを、青学周辺の事例を通して、議論をしながら学ぶ。
|
|
建築デザイン論
|
建築のデザインを形態的に扱うのではなく、それを生み出す社会や歴史、自然や地域の環境、人々の生活様式や心理との関係を中心に、主要な事例を用いながら基礎的理論を指導する。見学やスケッチ等を用いた描写訓練も同時に行う。
|
|
公共社会論
|
社会において人が人と共にどのように生きていくか、本講義では、戦後日本における公共性とその未来というテーマを立て、文化を学び、社会で活動する上で必要な最低限の理解と知識をもってもらうことを特徴とする。
|
|
経済と文明
|
社会科学と人文学を架橋する経済史学の方法論を基礎に、歴史上に現れる諸社会の経済における普遍性と同質性、文化における多様性と異質性を総合的に捉えることにより、人類の現代的課題に創造的に取り組む力を育む。
|