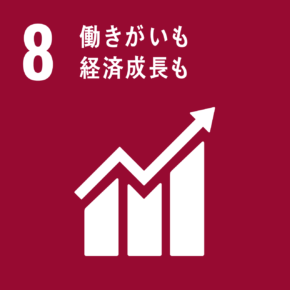- MENU -
POSTED
2025.04.21
TITLE
【AG150】ジェフリー・G・ジョーンズ教授(ハーバード大学ハーバード・ビジネス・スクール)「Deeply Responsible Business」 ~ビジネス・エシックスとリーダーシップ~開催報告
2025年3月29日(土)、青山学院創立150周年を迎えた2024年度における最後のイベントとして、米国ハーバード・ビジネス・スクールのジェフリー・G・ジョーンズ教授を招聘し、「Deeply Responsible Business」 と題した講演とパネルディスカッションを本多記念国際会議場(大学17号館)にて開催しました。
細田髙道 国際マネジメント研究科長より
150周年を飾る最後のイベントとなる講演会ですので、この講演会をいかに青山学院らしいインベントとするかについて頭を悩ませました。「青山学院らしいイベントとは?」についてはさまざまな考え方があると思いますが、私共は児童、生徒、学生、校友、教職員から保護者まで、設置学校の枠を超えて一堂に会する場であること、さらに創立150周年を迎えた本学の精神「サーバント・リーダーの育成」に至適な講演内容を提供することと定義いたしました。そこでまず、青山学院、青山学院大学、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科の共催で開催することといたしました。さらに講演会のご案内は大学だけでなく、各種設置学校および校友会のご協力を得ながら、できるだけ多くの方々の目に触れるよう努めました。おかげさまで事前参加登録者数は450人を超えました。

山本与志春院長による開会挨拶
ちょうど3月末は桜が咲き始めた頃であり、青山学院として最も美しい時期にお迎えできました。そして青山学院のスクール・モットーである「地の塩、世の光」、そしてAOYAMA VISION 160にも示されているとおり、すべての人と社会のために未来を拓くサーバント・リーダーを育成することが青山学院の使命であり、また、わたしたちはサーバントでありリーダーでもあり続けることをこの難しい時代にどう達成するのかについて、進むべき道を示していただける講演内容となることに感謝いたします。


ジェフリー・G・ジョーンズ教授 講演概要
ジョーンズ先生の講演は、過去から現代に至るまでにビジネス倫理や責任についてどのような考え方や捉え方があったのかの説明から始まりました。多くの問題はシステム全体に関わる問題であり、そのシステムはどう変えればよいのか、あるいはどこから始めるべきか、また利害が対立する場合にはどのような選択をすべきかと問いました。そして、その大きなテーマをより考えやすい次元に落とし込むために資本主義を個々の企業とビジネスリーダーのレベルで再構築することが重要だと説明し、サーバントでもありリーダーでもあった多くの企業家たちを紹介しました。
そしてウォレス・ドナム氏(元ハーバード・ビジネス・スクール研究科長)の1927年のスピーチを引用しました。
「もしビジネスリーダーの多くが、コミュニティ内の他のグループに対して明確により深い責任感を持ってその権力と責任を行使することを学ばなければ、私たちの文明は間違いなく衰退の時期に向かって進むかもしれません。」

このスピーチをもとにしてジョーンズ先生は5つの大きな問いを提示しました。
1)文明を救うことができる深い責任感を持つビジネスはどのようなものか?
2)どうすればビジネスリーダーはそのようなビジネスを追求したいと思うのでしょうか?
3)良いビジネスは高い利益を生み出したのでしょうか?
4)もし歴史の中で深い責任感を持つビジネスが存在したのなら、なぜそれらは決して一般的なものにならなかったのでしょうか?
5)社会的な大きな課題に対して、公共政策はビジネスよりも効果的でより民主的に対応できるのでしょうか?それともそうではないのでしょうか?
これらの問いに取り組むため、ジョーンズ先生は18世紀までさかのぼり、個々のビジネスリーダーのキャリア、動機、影響を調べ、リーダーたちが深い責任感を持っているかどうかを研究したそうです。対象となったリーダーの中には渋沢栄一氏も含まれていました。
人格的美徳および人生における究極的な意味と目的を見つけようとする精神性を備えたビジネスリーダーたちには、財務的利益は目的達成のための手段に過ぎず、目的そのものであるべきでないという価値観を共有している特徴が見受けられると説明しました。このような価値観はどのようにすれば教えることができるのかという問いから、ジョーンズ先生は教育機関の重要性にも言及しました。社会システムが大きく変化するには個々の人々が新しいマインドセットを持つことが必要であり、マインドセットの醸成には教育機関が大きな影響力と責任を担っています。また、リーダーの価値観の大半は初等・中等教育で培われるものであり、そこでの教育は再評価される必要があると力説しました。

パネルディスカッション
講演後はパネルディスカッションを実施しました。パネラーはジョーンズ先生に加え、申惠丰教授(法学部ヒューマンライツ学科、ジェンダー研究センター長)、島田由紀教授(国際マネジメント研究科)、そして細田髙道教授(国際マネジメント研究科長、持続的サプライチェーン研究所長)が登壇し、各自の問題意識について短いプレゼンテーションを行いました。申先生は価値と文明、そしてグローバル企業の責任に言及後、社会課題の解決に資するビジネスについての考えを説明しました。島田先生はキリスト教教育と人格教育、コミュニティに根差した経済活動について、スクール・モットーと関連させながら青山学院における教育について考えを述べました。細田先生からは、社会システムの課題を政府、ビジネス、個人の3つの視点から捉える考え方について説明がありました。


質疑応答
最後に質疑応答の時間をとりました。高等部3年生の久松真和さんから、「日本の学生は世界情勢や環境問題に関心が薄い傾向がありますが、この日本の状況に対してご意見をいただきたい。そして講演で紹介されたような深い責任を伴う価値観を持ったリーダーになるためにはどのようなことを今から行っておくべきかについて教えていただきたい。」と質問がありました。ジョーンズ先生は、「世界で起きていることに常に関心を持ち、認識をすることがまず重要です。その上で意見を交換して議論し、例えばウクライナや米国でどのような問題が起きているのかについて把握し、自分事として考え続けることが最初にすべきことではないでしょうか。」と回答しました。


終了後
全プログラム終了後、ジョーンズ先生はステージから会場に降りて、多くの生徒・学生さんと意見交換の場を持ち、有意義な時間を過ごしました。その後の慰労会において、ジョーンズ先生は近い将来に青学の高等部生と対話する機会を持つことを望んでいました。本イベントの主旨であった「青学らしい」イベントがまさに成就した瞬間でした。