- MENU -
在学生が語る、比較芸術学科ならではの魅力
ここで学んだからこそ得られたこと、素晴らしい経験について、4年生の3人に、たっぷりと語り合ってもらいました。

3領域を代表して集まってくれた3人。左から、瀬間海結さん(音楽・広瀬ゼミ)、窪野杏香さん(演劇映像・三浦ゼミ)、阪井健太さん(美術・水野ゼミ)。
――まずは、この学科を志望した理由に ついてお聞かせください。
阪井
僕は青山学院高等部からの内部進学です。絵を描くのが好きで、中学・高校と美術部に所属していました。美術はこれからの人生でずっと付き合っていく分野だと思ったので、ちゃんと学んで財産にしたいと入学しました。高等部を受験するときにはもう、そんな志望があって。当時から、この学科は1年次で芸術全般を学び、2年次から徐々に領域を絞り込んでいく、そして3年次でゼミに入り、自分で自由に研究できる、というくらいは知っていました。
窪野
私は静岡出身で、大学進学を機に上京しました。高校時代は、「ものを知っていること」にアイデンティティーを感じていたところがあって、あんまり学校になじめなかったんです(笑)。夜な夜な画集を眺めるうちにシュルレアリスムに触れて、こんな面白い世界があるんだ! と思って。高2の終わりくらいに、そういう芸術を勉強するのは面白いかもしれないと考えたとき、比較芸術学科の存在を知って志望しました。双子の妹も一緒にシュルレアリスムにハマっていて、妹にこの学科のホームページを教えてもらったことがきっかけです。
瀬間
私は小学3年生から7年間、「ピティナ・ピアノコンペティション」というコンクールに参加していました。このコンクールは、4つの時代背景に分かれた課題曲から選んで演奏するのですが、その時代に沿った演奏方法が求められます。プロの演奏家や音楽研究家の楽曲分析を参考にするうちに、楽曲分析に興味を持つようになって。高校の音楽の先生に「そういう学びができる学科はありますか?」と伺ったら、広瀬大介先生のクラシック音楽についての著作を紹介してくださったんです。それを読んで、広瀬先生のもとで楽曲分析を学びたいと思って、比較芸術学科に入ろうと決めました。
音楽や演劇映像の領域も勉強する中で、芸術はつながりがあることを体系的に学べました
――入学してみて、どのように感じましたか? 1年次で覚えていることがあれば、教えてください。
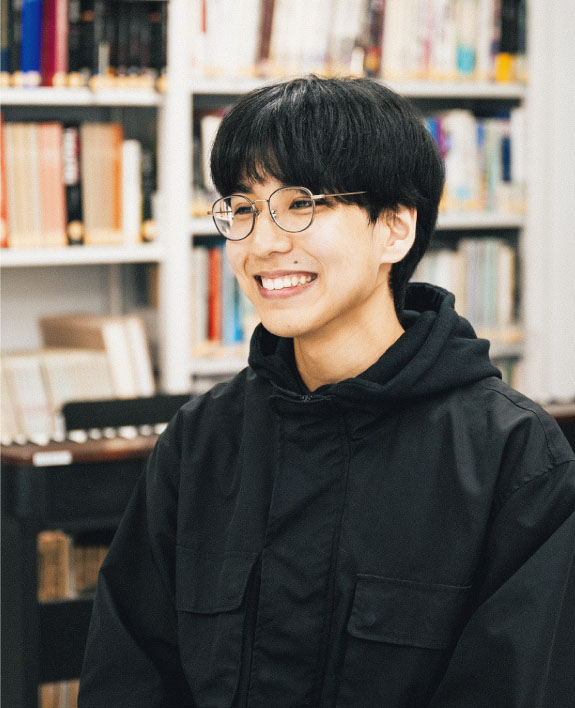
阪井
最初はそれほど美術の鑑賞の知識がなかったので、やる気はあったけれど、授業についていけるか不安でした。でも1年次の授業では、鑑賞の基礎を丁寧に教えてくださって。音楽や演劇映像の領域も勉強する中で、それぞれの芸術はつながりがあることを体系的にしっかり学ぶことができて、ここに入ってよかったなと思いました。
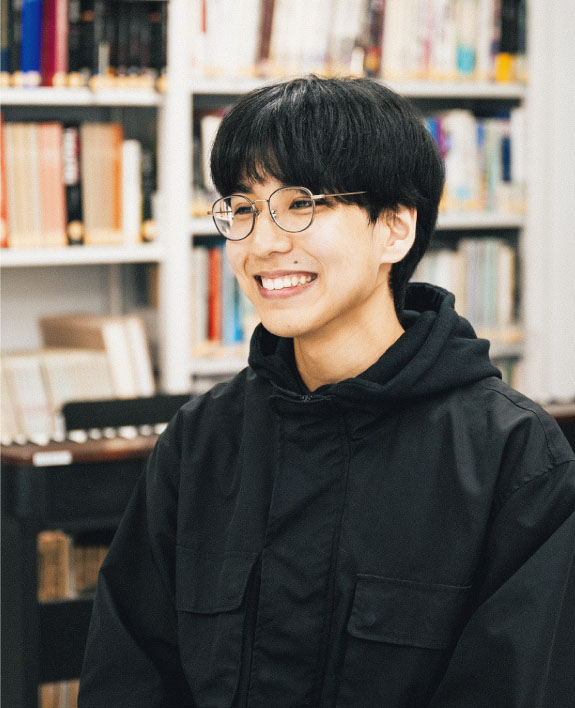
窪野
入学した当初は絵画を学ぼうと思っていたけれど、ここでは必然的に他の分野も学ばなければならなくて。私は音楽について知見が深くなく、難しかったんです。だから音楽は自分なりに頑張りつつ、絵画、映画、演劇の方面を目指そうと、1年のときに意志は固まりました。あとは、表現することをごく当たり前にやっている人が多い学科だと思いましたね。自分は知識を得ることに重きをおいていたんですが、影響を受けて、小説を書き始めました。
阪井
絵を描いている人と音楽をやっている人は本当に多いですね。僕は美術部に入っているんですけれど、美術部で精力的に活動している、比較芸術学科の同級生がたくさんいます。研究したいというだけではなくて、自分で表現したいという人が多い。
瀬間
私も音楽ばかりやってきたので、演劇映像や美術でどんな学びができるのか、不安がありました。入ってみると、1年次ではいろんな分野をバランスよく学べて。座学はもちろん、課外ワークショップでオーケストラを見に行ったり、美術館に足を運んだり、そうして実際に体験して、芸術を肌で感じられるのが、深い学びにつながっていると思います。
阪井
1年次の課外ワークショップでは、歌舞伎や文楽にもみんなで行きました。オーケストラはともかく、歌舞伎や文楽は自分で見に行く機会がなかなかない。それから、その分野に詳しい友人から話を聞きながら見られるのは、ぜいたくだなと思いました。自分一人でチケットを取って見に行く以上の価値がある。
瀬間
ただ行って終わりじゃなくて、帰り道に感想をシェアできるのが楽しいし、学びにつながっています。ほかの人の感じ方とか、それぞれが得たものをシェアできるのは、みんなで行く意味だと思います。
自分の好きなことが一つあれば、大丈夫。学びを日常生活の延長線上に組み込める学科です
――課外ワークショップの後は、必ずレ ポートをまとめるんですよね。比較芸術 学科はレポートの提出が多いそうですが、それはいかがでしたか?
瀬間
感じたことはあっても、それを言語化するのがすごく難しくて、葛藤した記憶があります。やっぱりそれは、何度も書くことによって、表現の仕方、言葉への表し方が分かってくる。
楽曲分析は、その曲の時代背景や、作曲家ごとの作曲法や構成を分析するのですが、回数を重ねるごとに、それほど難しいものではないと分かってきます。楽曲分析をすることで、楽譜はただの紙っぺらではなくて、その奥に広がっているものが見えるというか、その作曲家がどういう思いを持って作曲に取り組んだのかも見えてくるんです。
阪井
最初は「〇〇がきれいでした」といった、感想文みたいなことも書いてしまっていたかも(笑)。書く経験を何回も重ねる中で、自分の感情や印象の根拠がどこにあるのか、ほかの作品や他分野の芸術とも比較しながら論じることが少しずつできるようになってきました。僕は西洋美術史の研究ゼミに所属しているんですけど、そこで研究を発表した後に、今後はどういう方向性で進めていくべきかという展望を広げるフィードバックを、ゼミの水野先生がしてくださいました。研究をしていると、参考文献を探すのが本当に難しいと実感しているのですが、それも提示してくださって。そんなサポートもあって、自分で方向性を決めて、主体的に研究を進めていく姿勢が身についたと思います。

窪野
三浦ゼミでは、意外と忘れがちな映画本来の見方・楽しみ方を何度でも教えてもらえます。「この映画、こういう見方もできますよ」と、いろいろな捉え方をしていいんだと気づかされました。世間には、「この作品はこういうものだ」といった決めつけもあふれていますが、映画って本来そういうものじゃない。ゼミという場所で、専門的に映画を学んでいるからこそ、分析的な視点は忘れずに、でも、堅苦しい考えは持たずに映画を見ることができているのかなと思いますね。
1年次では、自分はレポートを書くのは得意だけど、話すことでは自分の言いたいことを全く伝えられないと思っていました。何か誤変換されて伝わってしまうような。ここで学んで考えを深めていく中で、納得のいく討論が少しはできるようになった気がします。

言葉にすることが怖くないというか、受け入れてもらえる環境が、ここにはあります
――さかのぼって、高校ではそういう話をできる人はいなかったのでしょうか?
窪野
私の地元は田舎なのもあって、「何それ?」と言われてしまうことがありました。ここでは、芸術をやっていても孤立感を覚えずに、芸術についてどこまでも突き詰めていくことができます。
阪井
学問として勉強しているからこそ、理論を組み立てて、感情論ではない議論が友人同士でできるように思っています。入学したばかりの頃を振り返ると、好きな音楽や映画のことを聞くのはいいけれど、「あ、そうなんだ。いいよね」くらいしか言えていなかった。今は、実際につくることの難しさも、表現している人が多いことも分かっているので、お互いの意見を尊重してリスペクトし合ったうえで、白熱した議論ができているのかなと思います。

瀬間
言葉にすることが怖くないというか、それをちゃんと受け入れてくれる環境がここにはあるなって思っています。年次が上がるにつれて分かち合えるというか、そんな環境を自分たちでつくっていっている。

――最後に、この学科を志望する方に向けて、メッセージをお願いします。
阪井
自分の好きな芸術の領域を4年間しっかり学べるのは本当に魅力ですし、その道の専門家の先生方であったり、一緒に同じ方向を向いて学ぶ学生と交流ができるのは、貴重な環境です。興味があれば、ぜひ! 個人で研究を行う以上に、 楽しく交流しながら知見を広げていけると思います。
窪野
私は入学前にはシュルレアリスムを学びたいと決めていましたが……比較芸術学科は、芸術で何かしら好きなものがあれば、別に詳しくなくても入って大丈夫な学科です。学校が終わってから渋谷のシアターに行ったり、美術館に行ったりと、自分の好きなことがあれば、学びを日常生活の延長線上に組み込むことができる。そんなに気負わず、でも、いろんなことにアンテナを張っていた方が、入学した後で楽しくなると思います。好きなことについての本を読んだり、絵や演劇などいろんなものを見て、 胸をときめかせることができる人は、すごく楽しい学科のはず。ここにいれば、変な人だって言われないで済むし(笑)。
瀬間
4年次になって振り返ってみると、私は入学前、ここで楽曲分析を学びたいと、そればっかり考えていました。比較芸術学科に入りたいと思っている人には、やっぱり受験勉強は大変だと思うんですけど、勉強の合間にこれまで見たことない映画を見てみようとか、聴いたことのない音楽を聴いてみようとか、今まで自分があんまり関わってこなかった分野にも、軽い気持ちでちょっとでも触れてみてほしい。そうして興味をどんどん広げていくことを心がけると、視野が広がって、大学生活がさらに充実したものになると思います。

