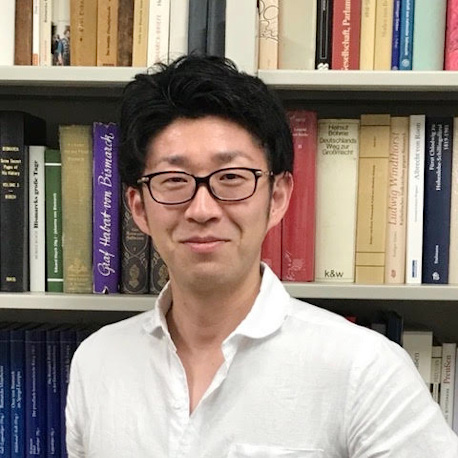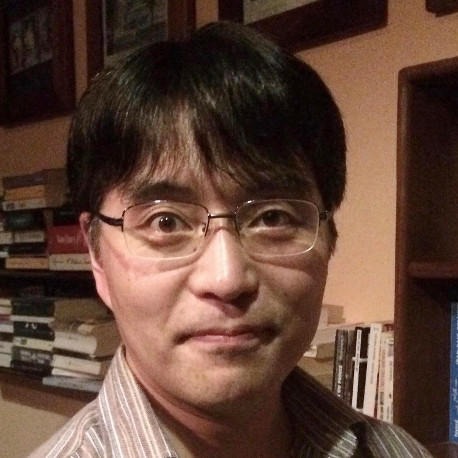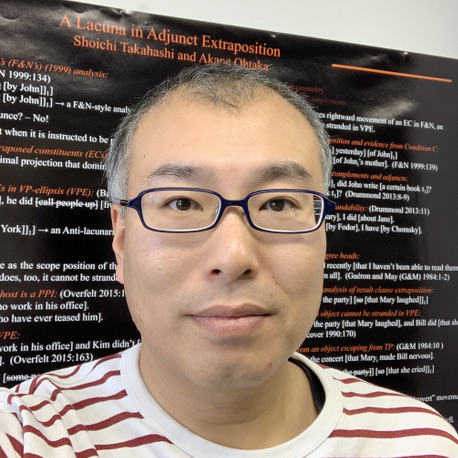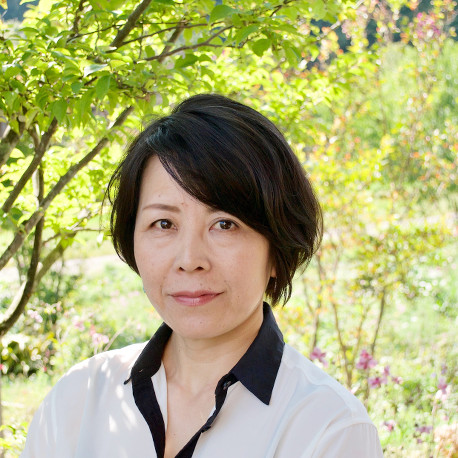- MENU -
-
もっと読む
20世紀以降のイギリス現代小説、特に、労働者階級出身のD.H.ロレンスやフェミニスト作家ヴァージニア・ウルフ、日本出身のカズオ・イシグロなどの作品を、階級、ジェンダー、戦争などのテーマに軸足をおいて研究しています。アウトサイダーの立場から小説を書く作家たちの声に焦点を当てそれをアップデートすることは、社会の主流から排除されがちな人々を尊重し、誰もが生きやすい世界を実現することにつながると考えています。
1,2 年生向けの授業では、幅広いイギリス文学作品のさまざまな「読みかた」を学べるように心掛けています。3,4 年生向けの授業では、自分の専門分野に近い小説を読み、おもに社会・文化的アプローチで作品を分析する訓練をしています。大学院では、さらに専門的な文学の精読と批評に重点を置いています。正しくわかりやすくて知性のある英語を使うことと日本語を使うことは、どちらも同じくらい大切です。たくさん本を読んで深い思考をして、自分の言葉を磨いてください。
Research Interests
イギリス小説
イギリス文学史
フェミニズム
戦争文化
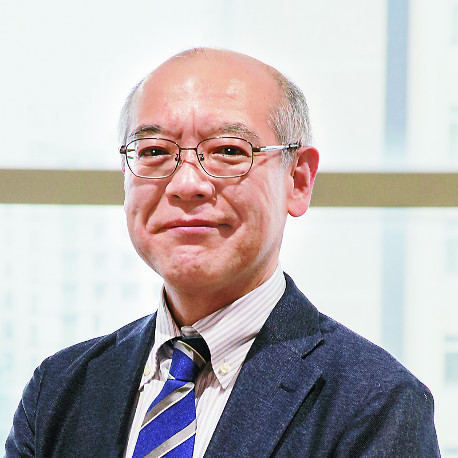
伊達 直之
Professor(教授、文学部長)
専門分野:英語詩・詩学・モダニズム文学と文化の研究, 英国・アイルランドの地域文化史、近代以降の芸術一般(特に美術と建築・庭園)、文化・メディア研究、メディア文化論、映像論、映画研究
担当授業:イギリス文化演習、イギリス文化概論I、II、英詩概論I、II など
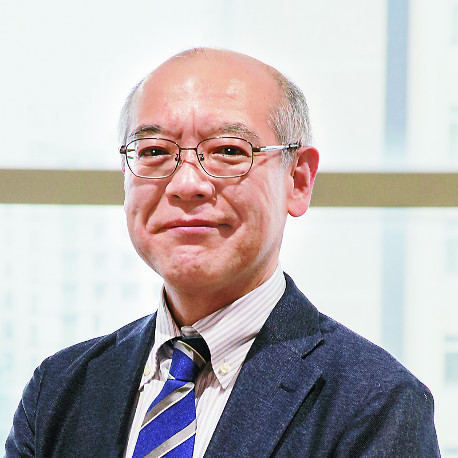
-
もっと読む
イギリスとアイルランドの文学と文化に関する授業を担当しています。
文学や映画やアニメ作品をひとつひとつ味わい尽くす快楽や喜びと同時に、それらの作品がある特定の時代や場所で生みだされて社会に受容されていくことの意味について、文化や歴史の大きな枠組みの中で理解すること、その深く広い面白さに魅了されて研究を続けてきました。この関係は、進化するWebやITと共に今も刻々世界中でリアルタイムに変化しています。だからいつも新鮮で、あきるということがありません。また新しい理解は、今とこれからの時代をどう生きるのかという、自分たちへの問いかけと行動に日々跳ね返ってくるので、毎日は充実します。(といっても、充実した毎日というのは、必ずしも楽々と平和に人生を生きていくことにはならないのですが・・・。)
最近のテーマは、戦争や紛争の表象における人々の「倫理」の働きや、日本、ヨーロッパ、米国の詩・歌の比較研究などです。個人的なキーワードは「中庸(ちゅうよう)」でしょうか。
Contact Info:yukidate@cl.aoyama.ac.jp

Joseph V. Dias
Professor
Intercultural Communication, TESOL
専門分野:TESOL(他言語話者に対する英語教授法), CALLコンピューターの長所を活かして語学学習をサポートする教授法, 患者と病院関係者間のコミュニケーション

-
もっと読む
Joseph V. Dias, originally from San Jose, California, is currently the co-coordinator of the Integrated English (IE) Program and a member of the Communications Unit of the English Department. He is responsible for seminars and lectures on Intercultural Communication, food culture, and the application of critical thinking to Web sources. His research interests include computer-assisted language learning, intercultural collaborative exchanges, and autonomy in language learning.
Currently a reviewer for the JALTCALL Journal and the program chair of the Lifelong Language Learning SIG of JALT, he has published articles that appeared in the following TESOL texts:
Dias, J.V., & Kikuchi, K. (2010). Designing listening tasks: Lessons learned from needs analysis studies. In Teaching Listening: Voices From the Field (N. Ashcraft and A. Tran, Eds.). Alexandria, VA: TESOL, pp. 9-31.
Dias, J.V. (2009). A Web of Controversy: Bringing Critical Thinking Skills Online. In Adult language learners: Context and innovation (G. Strong and A. Smith, Eds.). Alexandria, VA: TESOL, pp. 97-105.
More recently, he worked with Professor Onodera on the book Periphery: Where Pragmatic Meaning is Negotiated:
Dias, J. V. (2017). Sort/kind of at the peripheries: Metapragmatic play and complex interactional/ textual effects in scripted dialog. In N. Onodera (Ed.), Periphery: Where Pragmatic Meaning is Negotiated [Hatsuwa no Hajime to Owari: Goyoron teki Choosetsu no Nasareru Basho] (pp. 187-219). Tokyo: Hituzi Syobo.
Research Interests
Computer-assisted language learning
intercultural communication
intercultural collaborative exchanges
autonomy in language learning
TESOL
-
もっと読む
私の研究領域は、20世紀後半から現代にかけての英語で書かれた小説です。「英語で書かれた小説」というまわりくどい言い方をするのは、イギリスやアメリカの小説ではなく、アフリカ、インド、カリブといった様々な地域から出てきた作品を指すためです。かつて、西洋列強の帝国主義の拡大の結果として植民地となったこうした地域では、独立以後、英語やフランス語など支配者の言語で創作する作家たちがあらわれました。こうした作家たちによる作品群は「ポストコロニアル文学」(postcolonial literature)と総称されます。植民地主義による収奪、独立国家が直面する困難、混淆的なアイデンティティなどを主題にしながら、現在にいたるまで実に豊かな発展を遂げてきました。
こうした旧植民地地域から出てきた文学作品への関心が私の縦軸だとすれば、横軸となるのがナショナリズムに対する理論的な興味です。植民地支配からの独立を目指しナショナリズムを鼓舞しようとした人々が直面したのは、被植民者の集団内における民族的・言語的・宗教的な多様性でした。雑多な集団をどうやって「ひとつ」にすればいいのか、そもそも「ひとつ」という状態は幻想としてしかありえないのではないか、「ひとつ」であろうとすると必然的に誰かを排除/抑圧してしまうのではないか。1980年代以降に急速に発展したナショナリズム論は、こうしたやっかいな問題を考え抜いてきました。私は、ナショナリズム論の知見に依拠しつつ、ポストコロニアル文学を読んでいます。
縦の「ポストコロニアル文学」、横の「ナショナリズム論」、この2つの軸から成る私の研究領域をさらに複雑化するのが「グローバル化」と呼ばれる現象です。もっぱら経済的・政治的な現象として語られるグローバル化ですが、その波は文学研究にも押し寄せてきました。近年、「世界文学」という用語が取り沙汰され、従来の一国単位での文学研究を刷新し、世界全体を見渡す文学研究の方法が模索されています。これは、国を「ひとつ」として考えることのメカニズムを解明しようとするナショナリズム論の有効性が試される契機でもあります。また、言うまでもなく全人類が共有する課題である地球温暖化と気候変動は、単なる一国/一地域の人間としてではなく、共通の運命を生きる人類の一部としてみずからを捉えること、すこしおおげさに言えば新たな人間像を想像することを要請しているように思われます。茫漠としていながらも確実に見過ごすことのできない「グローバル」という思考の枠をどう捉えればいいのか、そしてどのように文学研究がそこに介入していくのか、作品と理論の研究を通じて考えていきたいと思っています。
研究関心
ポストコロニアル文学/理論
ナショナリズム論
世界文学論
-
もっと読む
私の研究領域は,広くは,外国語としての英語教育 (TESOL) と第二言語ライティング (Second Language Writing) です.その中でも特に「詩」や「俳句」といったジャンルを用いたクリエイティブ・ライティングを専門としています.クリエイティブ・ライティングという領域を研究対象とするようになったきっかけは,アメリカの大学院に在籍していた時に経験したライティングの課題でした.日本で英語をしっかり勉強してきたにもかかわらず,自分の主張が相手に伝わらない,文法的に正しい文章が書けるのに,自分の想いを読み手に理解してもらえないという苦い経験が,「自己表現力」を養うためのライティング指導とはどうあるべきかという問いにつながっていきました.そこで,先行研究を読み込み,実証研究を重ねる過程で,日本固有の文化である俳句を英語学習に取り入れることでこれまでとは違うライティング教育が展開できるのではないかと考えるようになりました.
この研究課題に取り組むべく,そして自己表現力育成のためのライティング指導法開発のために,様々な視点から実証研究を行ってきました.具体的な研究内容は,日本人英語学習者が作成した詩や俳句の言語学的特徴の解明,書き手の心の声(voice)とアイデンティティの表現方法の調査,英語ライティング能力向上との関連性の検証,そしてルーブリックを用いた評価基準の考察などです.また,クリエイティブ・ライティング活動で育成されたvoiceを表現する力が別のジャンルの文章にも転移するのかという問いの探究に向けても研究を進めています.
授業では,ライティング教育・研究のみならず,英語教育全般を扱っています.英語による「自己表現力育成」をキーワードに,第二言語習得論における最新の知見をおさえながら,現代の英語教育における課題や問題点を整理し,社会や学習者のニーズに沿う新しい英語教育のあり方を探っていきます.
Research Interests
英語教育学(TESOL)
第二言語ライティング(Second Language Writing)
クリエイティブ・ライティング(Creative Writing)
-
もっと読む
通訳実務経験に基づき研究を進め、現在の研究テーマは、放送ジャーナリズムにおける通訳、通訳教育、職業としての通訳です。
担当する通訳・映像翻訳のクラスでは、実践的なコミュニケーション・スキルの習得を目指しています。理論と実践の両面からアプローチ、これを通じてグローバルな視点での発想や活動を可能にするさまざまなコンピテンスの諸相について検討しています。
-
もっと読む
私の専門領域は、言語学の中の統語論という分野で、人間が単語を組み合わせて文を作っていく時にどのようなメカニズムが働いているのか、ということを研究する分野です。中でも、言語間の差異、例えば、日本語と英語ではどういうところが違うのか、それをどうやって子供が獲得するのか、そして、そのような差異は、人間言語が持っている普遍性の観点からどのように説明されるべきものなのか、ということに関心があります。
授業では、言語学でこれまで得られた知見を、受講者の皆さんになるべくわかりやすくお伝えするように心掛けています。一見難しく思える考え方が出てくることもあるかも知れませんが、一つ一つステップを踏んでいけば、きっと理解できると思いますので、辛抱強く頑張ってみてください。また、英語や日本語などの言語データを実際に分析して、「ああでもない、こうでもない。」と試行錯誤しながら、自分なりに考えてもらうプロセスも大事にしたいと思っています。普段何気なく使っている自分の母語であっても、皆さんが知らない、驚くような興味深い特徴や規則性がたくさんあります。そういった特徴や規則性を自分で発見できた時は、きっと感動ものだと思いますので、ことばに関心のある方は、私の授業に限らず、英語学関係の授業を是非受講してみてください。
Research Interests
統語論(Syntax)
CONTACT INFO:kasai@cl.aoyama.ac.jp
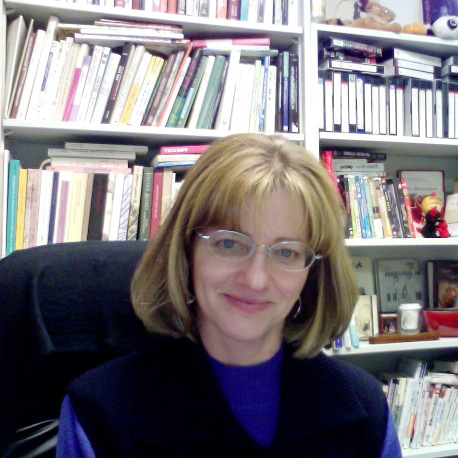
Mary Knighton
Professor
専門分野:American literature and culture
担当科目:Surveys in American Literature and Culture, Reading I/II, Special Topics courses in American Literature and Culture, Senior Seminar, Seminar for Graduate Students
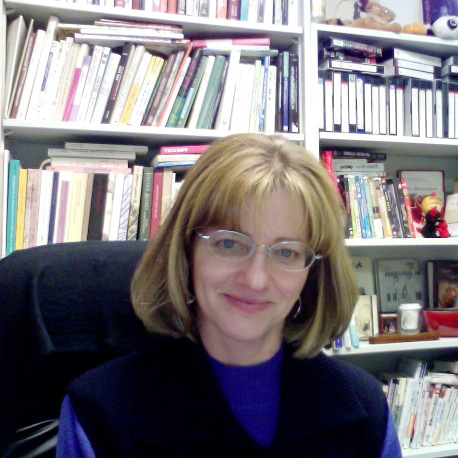
-
もっと読む
Mary A. Knighton, Ph.D., Professor of Literature in the English Department at Aoyama Gakuin University in Tokyo, has taught and published widely in both American and modern Japanese literature and culture. She received her Ph.D. in English, and two M.A.’s at University of California, Berkeley, where her research focused on Faulkner and American Modernism, the 19th-century slave narrative of Harriet Jacobs, and the short fiction of Kanai Mieko. Her research and articles have appeared in Faulkner and Print Culture, ed. Jay Watson (2017); Animal Comics: Multispecies Storyworlds in Graphic Narratives, ed. David Herman (2017); US-Japan Women’s Journal (2011); Japan Forum (2017); Notes & Queries (2017); and Faulkner and Twain, ed. Robert Hamblin (2009). Her current book project, Insect Selves: Posthumanism in Modern Japanese Literature and Culture, has been supported by JSPS KAKENHI Grant JP17K02663, ACLS/NEH/SSRC, and Virginia Foundation for the Humanities (now Virginia Humanities).
Research Interests
The research of Mary A. Knighton can be broadly divided into two areas:
(1) 19th-20th century American and British literature, and
(2) Modern and contemporary Japanese language, literature, and culture.
Studies in global modernism and transnational exchanges bring these two fields together. Related research interests include feminist, postcolonial, and critical theory; the multi-ethnic literatures of the US, particularly African-American literature; the American South; Gothic literature; visual texts, arts, and culture.
CONTACT INFO:mknighton@cl.aoyama.ac.jp
-
もっと読む
古くて新しいもの好き
現在はイギリス18世紀の文学、なかでも小説などの散文作品を主な研究対象にしています。しかし最初からこの時代に関心があったわけではありません。いろいろな国のいろいろな時代の小説をぼちぼち読んでいましたが、実のところは20世紀の実験的で前衛的な小説が大好物でした。新しいもの好きです。それがなぜ今は18世紀なのかというと、あるとき「小説の起源はどこだろう」と考えたことがきっかけで、大学院に進学して初期近代小説というくくりの18世紀のイギリス小説を研究対象に選んだからです。そこでは後に新しい「小説」というジャンルを立ち上げることになる試行錯誤の実験が様々におこなわれていました。そこに見られるまだ完成していないがゆえの自由さは、新しいもの好きにとって大変に興味深いものでした。さらに、この時代の歴史文化のあちこちで現代にまで繋がるような近代の萌芽を見つけられることが分かってくるにつれ、それまでの「新しいもの好き」は「古くて新しいもの好き」になっていました。
もともと英語への入り口は英語圏のポピュラー音楽でした。これに関しても大きな関心を持っていますが、こちら方面については英語圏を飛び出して広がった後、ぐるりと地球を一周。今はグローバルならぬ「グローカル」な音楽文化にもっとも魅力を感じるにいたっています。そこで伝統あるいは地域特性をともなった音楽的なルーツが再生される様を見れば、これもまた「古くて新しい」文化的な実践と言えるでしょう。
趣味形成に関する統計的な調査によると、大多数の人が10代後半から20代にかけて好んで聴いた音楽を一生聴き続けるそうです。私は古くて新しいものを発見しながら、この調査結果にあらがって生きていきたいと思います。
-
もっと読む
前を向きたくない、という甘えた動機で読書に没頭しているうち、文学を研究するようになっていました。使い古した辞典と洋書を、喫茶店や電車や街路に持ち込み、詩や小説の文字列に、遠くから響くささやきを聴こうとしていた私の学生生活は、申し分なく自閉的なものでした。しかしそれは同時に、厄介で魅力的な他者たちとの濃厚な異文化交流を、言語的・時代的な距離を介して渇望し続けていたという点において、あられもなく開かれた日々でした。
一つの事に一人で没頭しているつもりでも、共に在ってしまう、自分の世界と「外」をつなぐ通路が、必ずどこかに開いてしまう、という体験は、私個人に特有のものではありません。たとえばそこには、ローカルなものとグローバルなものが激しく混淆していた20世紀前半に、作家たちが詩や小説へ取り込もうとしていたダイナミズムと、連動するものが見出せます。またその混ざり合う運動感には、大学で多様な遭遇体験を享受するであろう皆さんに訪れる詩的な出来事とも、相通ずるものがあるはずです。
現在私は20世紀のアメリカ詩を研究しており、知名度的にも、ジェンダー / セクシュアリティ的にも、マイノリティに属する詩人たちに関心を抱いています。そのような詩人たちは、自らのマイナー性を、少数のあいだにおいてのみ共有可能な連帯感の発生源として用いるふしがありました。しかし生み出された詩自体には、閉鎖的な共同体を超えて広がる「世界」への開路が、至る所に生じています。インターネットにより、遠くの他者と繋がれる(と夢見られていた)環境が、我々を、近くの知人たちから成る親密圏に自閉させている昨今、遠くの詩人たちが喚起する数々の問題は、すぐれて今日的なトピックを呼び寄せます。我々の生活雑感に帯びる普遍的な私性と、過去の他人が書いた詩の私的な普遍性とが交差する契機を、皆さんと共に見出しながら、様々な問題に遭遇し直し、思考し、対話をしたいと思っています。
研究関心
アメリカ文学 (American Literature)
アメリカ詩 (American Poetry)
モダニズム (Modernism)
-
もっと読む
19世紀から21世紀にかけての英国の文学・文化が専門領域です。詩や小説がどのような形で読み手のもとに届き、どのような場で読まれ、知と喜びと想像力の源として、それぞれの時代においてどのように人々の日々の力になってきたのか、言葉が構築する世界が現実世界の読み手をどのように個別化し、かつ繋いでいくのかといったことに関心をもっています。現在は、ロマン主義時代の歴史小説やスコットランドの作家の作品を中心に、小説の概念や小説批評の歴史を再考したり、UKにおける文化的アイデンティティの展開と文学との関係について考察したりしています。特に、19世紀の作家Walter Scottの多様な近代的受容を通して、19世紀に小説が果たしていた社会的・文化的役割について検討しています。
授業では、日本語では「イギリス」と呼ばれている国の地域的・言語的多様性に注意を向けながら、作品成立の背景や読み手と作品との関係を歴史化すること、そのうえで、現代における文学の意義をともに考えること、そして何よりも、精読に基づいた自由な解釈をともに楽しむことを心がけています。
Research Interests
イギリス文学・文化(British Literature and Culture)
-
もっと読む
私の研究領域は音声学、言語学(音韻論)です。ことばを話し、聴き取って理解するプロセス全般に興味があります。このプロセスを、対話の場面に当てはめると、次のように考えることができます。話し手は、肺から空気を押し出し、喉・舌・唇などを動かして音声を発します。発せられた音声は、空気中を通って聴き手の耳に到達します。聴き手は、音声波の中に単語や文をみつけて、ことばとして理解します。この話し手と聴き手の結びつきは「ことばの鎖(the speech chain)」と言われ、話しことばは、両者の間で、様々な形式(音声を発するための活動→空気中の音声波→聴き取った音声の解読)に変換されることを表しています。私の現在の研究課題は「音声を発するための活動」を中心としています。
私たちは、複雑なメッセージを正しく伝達するために、喉・舌・唇などの動きを正確にコントロールしています。このような観点から、話しことばを生成するための調音活動と言語構造(音節構造、プロソディなど)との関係を調べています。この他にも、話しことばにおける発音変化、音形選択の要因、英語発音の多様性、外国語学習者の音声産出などに関心があります。
英語音声でも日本語音声でも、注意深く観察すると、色々な疑問や不思議なことに出会えます。授業では、受講者の皆さんが、専門的概念や理論的枠組みを正確に理解し、疑問に思うことを順序立てて考えることを大切にしています。更に、そのような活動を通して、疑問を解決するための、自分自身のアイディアを発見して欲しいと思っています。
Research Interests
音声学(Phonetics)
Speech Production & Perception
音韻論(Phonology)
CONTACT INFO:m_nakamura@cl.aoyama.ac.jp
-
もっと読む
言葉の壁の向こう側へ!
文学との出会いの頃を振り返ってみると、書物とは未知の世界や人生をのぞき見る場であり、引っ込み思案で内向的な子供だった私は、そこで自分という小さな殻の向こうに広がるものと最も自由に相交わることができた。そこで重ねた感情の経験が、大人への入り口で自分を造り、自分の日本語の感覚を造り上げる土台となった。
大学で米文学と出会い引き寄せられ始めた頃、英語力が不十分だった私は、辞書と首っ引きで原書と格闘しながら、気が遠くなったのを覚えている。こんな風に四六時中辞書を引き、蟻の歩みのように書かれている事柄を解読していて、外国語の文章が母国語を読む時のように、リズムや温度や質感までも自分なりに感じられる日は果たして来るのだろうかと。ただ、大学3年時に出会った南部作家のフォークナーやウェルティ、あるいは私が大学院でアフリカ系アメリカ文学を専攻するきっかけとなったトニ・モリスンらの作品世界の魅力と言葉の力には、言葉の壁を越えて心に響いてくるものが確かにあった。そこで作品と向き合い、ひとつずつ感情の経験を心に刻むうち、いつの頃からか英語は私にとって血肉の通ったものへと変容していった。
外国語の習得には、世界へ飛び出して行き異国の人々の意志疎通を図るための道具を手に入れるという側面と、個人の感性が異なる歴史や文化を担う言語と衝突して生まれる内面の経験を蓄積し言葉を我がものとしていく側面の2つがあるのではなかろうか。英米文学科に入った以上、その両方を手に入れて欲しいと思う。
野邊 修一
Professor(教授)
専門分野:コミュニケーション
担当授業:コミュニケーション演習、コミュニケーション概論、フレッシャーズ・セミナー、基礎演習、コミュニケーションB研究・演習(大学院)など
-
もっと読む
私の研究室では「人間のコミュニケーション」について研究しています。人と人が話をするとき(例えば日常会話や面接の場面で)、人は情報をどのように産出、伝達し、理解しているのでしょうか? 人は言語情報と、(顔の表情やジェスチャーなどの)非言語情報を扱っていますが、その表出の状態、それを可能にしている心的過程、さらに表出された情報を認識し理解する過程とは、どのようなものでしょうか?
この分野に興味を持つようになったきっかけは、大学時代、同じ人が同じ話題について話す場合でも、日本語と(英語などの)外国語で話す時、さまざまな違いがあることに気付いたことです。言語は当然ですが、声の調子、顔の表情やジェスチャーなどの非言語面、話す詳細な内容・構成やパターン、その人から受ける印象などが、時に大きく、時に微妙に違っていました。言葉を話し理解する時に、人の頭の中でどのような処理がなされているのかについて、それから徐 々に興味を持つようになりました。
私担当の「コミュニケーション演習」では、対人コミュニケーション論や言語心理学の立場から、人の認知・認識、英語や日本語の仕組み、言語・非言語 チャンネル上の情報表出、伝達、理解などについて議論しています。また、人間同士の対面インターアクションだけでなく、テレビ、映画、コンピューターグラフィクスエージェントなどの映像と、人がいかに関わり情報を処理しているのかについても考えています。
Research Interests
非言語コミュニケーション論
対人コミュニケーション論
言語心理学
英語教育
CONTACT INFO:snobe@cl.aoyama.ac.jp

大川 道代
Associate Professor(准教授)
専門分野:パフォーマンス・スタディーズ、スピーチ・コミュニケーション
担当授業:コミュニケーション演習、コミュニケーション特講、スピーチ・コミュニケーションII、メディア・イングリッシュなど

-
もっと読む
Bio
南イリノイ大学大学院スピーチ・コミュニケーション研究科、修士課程修了
獨協大学外国語学部、英語学科、非常勤講師
茨城大学教育学部、英語教育講座、助教授を経て
現在、青山学院大学文学部、英米文学科、准教授
Research Interests
パフォーマンス研究 (Performance Studies)、スピーチ・コミュニケーション(Speech Communication)
コミュニケーション教育 Communication Education)

小野寺 典子
Professor(教授)
専門分野:コミュニケーション、語用論、談話分析
担当授業:コミュニケーション研究 (大学院「談話標識の共時性・通時性」)、コミュニケーション特講, コミュニケーション演習(「談話分析」ゼミ)など

-
もっと読む
専門は、言語学の中でも人のコミュニケーションに関わる分野です。人の原始的・基本的行動の1つに「会話」があります。1980年以前の言語学では、高校の授業などでもよく習ってきた「文・語」を研究対象の中心にしていましたが、それ以降、文よりもっと大きな単位「談話」(language larger than 2 sentences)を対象として、談話分析という分野が立ち上がりました。談話は、書きことばと話しことばに分かれますが、特に日常会話を扱う話しことばの分析は、その中に生き生きとした人のコミュニケーション(研究ではインタラクションとよく呼びます)を捉えることが出来、おもしろいものです。私たちは、無意識的に会話をしていると思っていますが、実は、その中に驚くほどの規則性・パタンなどが見つかり、自分たちの会話の成り立ちが手に取るようによくわかるのです。例えば、日本語会話では、「うん・そうね・まじー?」といったあいづちをよく打ちますが、英語会話ではその半分位の量のあいづちしか打ちません。このことから、日本人はlistenership (聞いてますよ!と知らせること)を大事にしていると言えます。大学学部の授業では、ゼミでこの談話分析をやっています。
また、韓国語や日本語にはいわゆる敬語があり、目上や先輩に話すときには、この敬語を使います。英語やフランス語には敬語がないため、どうやって目上の人に話したらいいの?とは、英米文学科の熱心な学生がよく抱く疑問です。東アジアでは、昔から上下意識が人々の間にあり、毎日、その意識をもとにしたことば使用が繰り返され、敬語が作られていったと考えられます。言語が文化的特徴を反映させているところは、社会言語学で扱われますが、敬語の成り立ちプロセスは、文法化というメカニズムで説明でき、これは、歴史語用論という分野で扱われています。
最後に、私の趣味ですが、、、白銀の世界でのスキーが好きでしたが、最近はスポーツ観戦にはまり、特にテニスをよく見ます。大坂なおみ選手が C’mon! と頑張っていると、こちらまで頑張れますね! あとは料理など。C’mon!
Research Interests
言語学(linguistics)、語用論(pragmatics)、 社会言語学(sociolinguistics)、談話分析(discourse analysis)、歴史語用論 (historical pragmatics)
CONTACT INFO:onodera@cl.aoyama.ac.jp
-
もっと読む
Andrew Reimann (PhD, Applied Linguistics) teaches and researches intercultural communication, comparative culture studies and media literacy. He is from Vancouver, Canada and currently lives near Tokyo, Japan. Growing up in a bilingual family (English and German) and in a multicultural country (Canada), I was interested in how people could connect and communicate across differences. Intercultural communication uses language, observation and experimentation to unlock, explore and understand hidden differences for mutual benefit and exchange. I am looking forward to making new connections.
Globalization, interconnectivity and access to information have created both challenges and opportunities. Success requires being able to adapt, predict, improvise and pioneer new ideas while challenging old ones. Connecting with others and creating ideas that spread is the heart of intercultural communication.
My background and research interest is in social linguistics, with particular emphasis on intercultural communication. Although English is a universal language, in order to communicate effectively with people from diverse backgrounds, we need to understand their culture, values and perspectives. In class we work towards cultural awareness and global understanding by looking at examples in language, religion, history, culture media and current events. Recent projects and areas of interest include Media Literacy, cross-cultural humor and communication strategies.
Publications
Reimann, A. (2019). Culture Studies Handbook. Fifth Edition, Intergraphica Press. Tokyo, Japan. ISBN: 978-0-9891730-1-8
Reimann, A. (2014). Critical Incidents for Raising Cultural Awareness. In C. S. C. Chan & E Frendo (Eds.) New ways in teaching business English (pp. 258-264). Alexandria, VA: TESOL. ISBN 978-1-9311-8514-1
Reimann, A. (2012ss, Tokyo, Japan. ISBN: 978-4-6). Raising Cultural Awareness as part of EFL Instruction in Japan. LAP LAMBERT Academic Publishing, Akademikerverlag GmbH & Co. Saarbrücken, Germany. ISBN 978-3-659-18795-7

齊藤 弘平
Associate Professor(准教授)
専門分野:アメリカ文学・文化
担当授業:アメリカ文化演習(4)、アメリカ文化概論、アメリカ文学/文化特講 など

-
もっと読む
19世紀から20世紀初頭にかけてのアメリカ文学と文化、そして医学、心理学、経済学、精神分析などの隣接する諸科学との文学の影響関係を、主要な専門領域としています。特に「人間」「自己」「健康」というような、我々が当たり前の前提のように受け止めている概念やその定義が、どのように近代になってから、微妙にでも決定的に、変容してくるのか?ということに強く興味があります。現在は、アメリカの心理学者・哲学者 William James を中心に、文学作品から映画や絵画などの視覚文化も射程に入れながら、19世紀終盤以降の知識人やアーティストがいかにして「心/意識」を描いてきたのか、その大いなる発見あるいは大いなる誤解や失敗はどこにあるのか、そして世界大戦後の「治療的文化」とポップカルチャーだったり労働倫理だったりの深い結びつきをどう理解するか、などについてずっと考えたり、書いたりしています。
しかし授業においては、自身の専門にこだわらず、学生の皆さんへきちんと体系だったアメリカの歴史を教えること、その新興国から生まれる文学や文化のダイナミズムをさまざまな角度から紹介すること、ジェンダー、人種、労働などの現代的な社会問題を歴史的に文脈化した上で考えてもらうこと、を常に心がけています。ここ最近のゼミのテーマとしては、精神疾患、障害、などがどのように20世紀以降の文学や映画に表象されているのか、について学生たちと一緒に考察しています。
そもそもアメリカ文学や文化を専攻することになった動機は、少年の頃よりアメリカ産のRockやJazz、Hip-Hopなどのポピュラー音楽が大好きだったから、そしてアメリカ映画に夢中になっていたから、だと言えます。アメリカ文学には限らないですが、眠れない夜に小説を読むことも日課としていました。世を拗ねたカウボーイたちや自我の不安に悩むアンドロイドたちも、また私にとって人生の師なのです。
大学生の頃はバンド活動をしていたこともありますし、友人たちと自主映画を撮ったりなんかもしていました。スポーツ観戦も好きで、一時期の狂信は覚めましたが、日本ハムファイターズ(日本のプロ野球チーム)至上主義者です。移り気で分裂症万歳な気質もあるので、のめりこむ趣味もよく変わるのですが、最近の趣味特技について言うと、アナログレコードの洗浄とスパイスカレーづくりです。アナログレコードの溝をじっーと眺めていると、その向こうに宇宙が広がっているのがよくわかります。
Research Interests
アメリカ文学(American Literature)
アメリカ文化史(American Cultural History)
批評理論(Critical Theory)
知識史(History of Ideas)
-
もっと読む
16世紀から17世紀のイギリス文学、主にEdmund SpenserとJohn Miltonを中心とした韻文と、同時代の文学と政治や宗教との関係に関心があります。イギリスの歴史のなかで、唯一国王の処刑にまで至った動乱の17世紀。パンフレットを始めとして膨大な出版物が盛んにだされ、様々な政治・宗教的な主張が叫ばれた時代に、文学でどのような言説が産み出されてきたかを、当時の視覚的資料を比較しながら調査をしています。テレビもインターネットもなかった時代、「詩は絵のように」(ut pictura poesis) 広がる世界を通じて、みなさんの知的好奇心を高めてください(curiosityやwonderも17世紀のキーワードです)。専門は初期近代ですが、学生時代から14世紀中英語の文学にも関心を寄せています。
授業では、文学作品と絵画や挿絵などの視覚芸術の接点、音楽の使われた方なども紹介しながら、文学が持つ幅広い間口の一端を示すことができるようにしています。
CONTACT INFO:s_wataru@cl.aoyama.ac.jp
-
もっと読む
「言語には文法規則がある」ということは明白だと思いますが、実際にどんな規則があり、どうしてそのような規則があるのかということを明確にしようとすると、そんなに明白ではない、実に面白い性質が言語には存在するということが分かります。そのような言語の体系に、生成文法という枠組みを用いて理論的にアプローチすることが専門分野です。特に、文法は、言語の意味的情報とは独立して機能するシステムなのかということにずっと興味を持っています。
授業では、細かな理論的知識というよりは、言語とは本質的にどのようなものなのかということを理解してもらえるように心がけています。言語の構造を分析する際に、樹形図という図のようなものを用いるのですが、自分で書けるようになると理解も深まりますし、言語を分析するのが楽しくなると思いますよ。みんなで樹形図を書くエクササイズも行うので、英語学が初めてであっても大丈夫です。
子供の頃に観ていたロボットアニメが一因だと思うのですが、何かを操作したりすることが好きです。もちろんロボットは操作できないので、休みの日は、身近で操作できる車との時間を楽しんでいます。もしかしたら、樹形図も、ロボットではないですが、言語の設計図だから好きなのかもしれません。
Research Interests
統語論(Syntax)
意味論(Semantics)
統語論と意味論のインターフェイス(Syntax-Semantics Interface)
CONTACT INFO:s_takahashi@alum.mit.edu

田中 深雪
Professor(教授)
専門分野:通訳・翻訳研究(Interpreting and Translation Studies)
担当科目:コミュニケーション特講 I(5), II(5) 、コミュニケーション演習 I(7), II(7)
翻訳 I (1) 、 通訳基礎、通訳 I(1),(2)

-
もっと読む
主に通訳や翻訳研究、それに外国語の教え方を専門にしています。現在は、ある言語を他の言語に「訳す」といかなることが生じるのかといった点を探るべく、リサーチを進めています。たとえば通訳者が同時や逐次で訳す時、あるいは翻訳者や外国語の学習者が訳す時、何が加わり、差し引かれ、置き換えられ、脚色されていくのかを詳細に辿ることによって、異なる文化を訳すことの難しさ、奥深さを見出すことができます。また通訳者・翻訳者の歴史にも興味があり、江戸時代に長崎を中心に活躍したオランダ語の通訳者(蘭通詞)についてもリサーチを続けています。
授業においては、絵本やユーモアの翻訳、字幕翻訳や分析、アニメ作品とオリジナルの比較など身近な素材を用いて「訳す」ことの難しさと楽しさを実体験してもらっています。自分の語学力、知力を駆使して訳を生み出す作業は難しいですが、うまく訳せた時の喜びは代えがたいものです。このように「訳す」作業を実体験することによって、通訳や翻訳がどんな仕事なのか、さらには通訳者や翻訳者が異言語間、異文化間コミュニケーションにおいて、どんな役割を果たしているのかという点を考えるきっかけになればと願います。
Research Interests
通訳・翻訳研究(Interpreting and Translation Studies) 外国語としての英語科教授法(TESOL)
-
もっと読む
専門はイギリス文学・文化です。19世紀、なかでもヴィクトリア時代後期(「世紀末」と言われることが多い)を主に研究しています。文学者でいえば、ウォルター・ペイターとオスカー・ワイルドについて比較的多く論文を書いていますが、文化史の研究者として、文学にとどまらず、美術、映画、演劇、音楽の諸芸術に加えて、ファッション、経済、政治などにも研究対象として興味を持っています。翻訳の仕事も好きです。
そのような拡散する個人的関心と大学教育の社会的役割への私見をすり合せた結果、ゼミでは「比較企業文化研究」と称して、文化的背景の分析をベースとして、現代の(そして未来の)企業活動について学生の皆さんと考察する作業を行っています。イギリス文化の研究者としては、古典や美術などを中心に、イギリスという国がヨーロッパ大陸との文化的交流(この言葉が自ずと想起させる穏やかなものでは必ずしもないのですが)のなかで自己形成を果たした経緯にいま最も大きな関心を寄せています。イタリアとフランスの言語と文化にも愛着があり、2019年度は在外研究でヴェネツィアとパリに滞在します。
研究関心
イギリス文学 (English Literature)、文化史 (Cultural History)
CONTACT INFO:ytanaka1102@gmail.com
-
もっと読む
私の専門分野は英語史ですが、英語の史的研究と言うと過去の古い英語を対象にしているといった印象が強いのではないでしょうか。確かに、従来の英語史研究では、英語が比較的大きな変化を遂げた古英語から近代英語にかけての時期が主要な考察対象であり、20世紀以降の現代英語は英語史の研究領域とは見なされていませんでした。私自身の研究領域の一つも古英語(1100年以前の英語)です。
しかし、近年、British National Corpus,Corpus of Contemporary American English,Corpus of Historical American English, Corpus of Global Web-Based Englishなど、現代英語に関する大規模な共時・通時電子コーパスが利用可能になり、20世紀以降の英語におこっているさまざまな通時的変化や世界で用いられている英語(Englishes)の多様性が明らかにされつつあります。そうした新たな潮流の中で、「現代英語の多様性と変化」が私の新たな研究テーマとなっています。
私の授業では、英語の歴史的側面を扱うことが多いかと思いますが、そのことによって学生の皆さんの現代英語への理解がより深まるように努めていきたいと考えています。
Research Interests
英語史(History of English)
現代英語の変異・変化(Variation and Change in Present-day English)
中世英語英文学(Medieval English Language and Literature)
CONTACT INFO:zj8j-trsw@asahi-net.or.jp
-
もっと読む
アメリカ演劇との出会い
アメリカ演劇の中でも最高傑作と思われるのは、ユージン・オニール (Eugene O’Neill) の『夜への長い旅路』 (Long Day’s Journey into Night)です。この作品と出会ったことで、私は演劇を専門とするようになりました。有名な舞台俳優だった父と、麻薬中毒患者だった母をモデルに、作家自身の家庭の崩壊を描いた自伝的な作品です。修道女かピアニストになることを夢見る少女だった母は、父と結婚するためにどちらの夢も捨てるのですが、表向きは華やかでも公演のために次々と安ホテルを移動する俳優の生活に疲れ果ててしまいます。また出産の際にホテルの医師にモルヒネを処方されたことがもとで麻薬中毒になってしまいます。20世紀初頭の中流家庭の理想的母親像である「家庭の天使」の役割を必死で果たそうとしながら、理想像とはかけ離れた自分を嫌悪するあまり、ますます麻薬に逃げ込んでいく母の姿には、消極的には見えますが、現在の女性と変わらない、抑圧された強い自立への欲求を見ることができます。最終幕、花嫁衣裳を手に麻薬に溺れ、幸せだった過去にだけ生きようとする母の姿は、女性の(できる範囲での)自己主張を劇的に描いた場面だと言えます。
文学批評の役割はテクストの中で声なき者たちがどのように位置付けられているかを解きほぐすことだ、と述べたのは批評家のガヤトリ・スピヴァックですが、『夜への長い旅路』は私にとってそのような批評の出発点となっている作品です。
-
もっと読む
専門はアメリカ小説です。現在の研究テーマは、初期アメリカ文学におけるニューヨークの意義について再検討を加えています。他にも、18~19世紀建国期文学、女性文学、家庭小説、書簡体小説などに関心を持って研究を行っています。
担当している授業は、アメリカ文学史やアメリカ文学・文化関連の演習です。クラスでは、文学作品を精読することはもちろん、時代背景などの資料も取り入れながら、文学を体系的に理解することを心掛けています。
-
もっと読む
主に発音関係の授業を担当しており、英単語のアクセントはどんな法則に従っているかというような問題が大きな関心事です。少し具体的に述べますと、普通の基本形の場合と派生形の場合では強く発音する部分が違うことがあります。例えば、< >を強い部分とすると、drma, cid, rtistなのに、dramtic, acdity, artsticです。こういったことの説明方法はいろいろあるのですが、音韻論という「<人間>が語句や文を発音する際のメカニズム」といった観点からはどのようなものなのかということが大きなテーマと言えます。
担当科目の英語音声学は、英語の発音に関する知識と技術を身に付ける入門的な科目です。一般にゼミと呼ばれる3~4年生向けの少人数クラスでは、(今後変わるかもしれませんが、)今世紀になってからはずっとイントネーションを扱っています。また、必ずしも毎年度担当するわけではありませんが、スペリングと発音の関係の授業を持っています。ちょっと数学的な接近方法で、正確かつ実用的な規則を身に付けつつ、「音韻論」的なもののと捉え方に触れるというようなことを行っています。
Research Interests
英語学 (English Linguistics), 英語音声学・音韻論 (English Phonetics/Phonology).
-
もっと読む
Yuki Masami (her name follows the Japanese convention in which the family name precedes the given name) teaches courses in ecocriticism, environmental humanities, and American literature and culture. She studied ecocriticism in the world’s first graduate program in literature and environment at the University of Nevada, Reno, in 1996-1998 on Fulbright, and received her Ph.D. (English) in 2000. In research and teaching, Yuki has focused on such topics as food in a toxic age, biocultural diversity, literary soundscape, and a discourse of survival in the Anthropocene.
Yuki’s books include Foodscapes of Contemporary Japanese Women Writers (translated by Michael Berman, Palgrave Macmillan, 2015; Japanese original in 2012), Ecocriticism in Japan (co-edited with Hisaaki Wake and Keijiro Suga, Lexington Books, 2017), and Ishimure Michiko’s Writing in Ecocritical Perspective: Between Sea and Sky (co-edited with Bruce Allen, Lexington Books, 2016). She has published numerous articles and book chapters including those which appear in ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment, The Routledge Companion to the Environmental Humanities (edited by Ursula Heise, Jon Christensen, and Michelle Niemann, Routledge, 2017), A Global History of Literature and the Environment (edited by John Parham and Louise Westling, Cambridge University Press, 2017), The Routledge Handbook of Ecocriticism and Environmental Communication (edited by Scott Slovic, Swarnalatha Rangarajan, Vidya Sarveswaran, Routledge, 2019). She is a series co-editor, with Scott Slovic and Joni Adamson, of the Routledge Environmental Humanities. Yuki also served as president of the Association for the Study of Literature and Environment in Japan (ASLE-Japan) from 2016 to 2020.
Research Interests:
Ecocriticism / Environmental Humanities
Contemporary American Literature and Culture
Comparative Literature
CONTACT INFO:yuki.masami@cl.aoyama.ac.jp