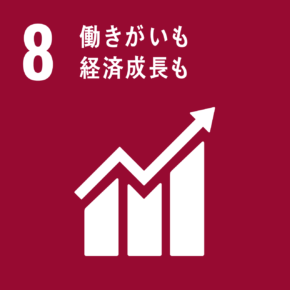- MENU -
POSTED
2024.07.22
TITLE
公益財団法人山田進太郎D&I財団と協力して、STEM(理系)領域の学生生活を体験できるプログラム「Girls Meet STEM College」を開催

青山学院大学は、公益財団法人山田進太郎D&I財団(以下、山田進太郎D&I財団)と協力して、研究室ツアーや大学生との交流等を通して、中高生女子が楽しくSTEM*分野の学びや実際の学生生活を体験できる「Girls Meet STEM College」を2024年7月14日(日)に相模原キャンパスで開催しました。
*STEM・・・科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、数学(Mathematics)の4つの教育分野の総称

【山田進太郎D&I財団についてとイベント開催経緯】
山田進太郎D&I財団は、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)の推進を通じて、誰もがその人の持つ能力を発揮し活躍できる社会の実現を目指し、2021年7月にメルカリCEO山田進太郎氏によって設立された公益財団法人です。特にSTEM(理系)のジェンダーギャップに注目し、中高生女子がSTEM分野への進学やキャリアを検討し、自己決定する機運を高めることを目的に、奨学助成金事業を展開しています。2024年より「Girls Meet STEM」事業を開始し、企業でのオフィスツアーや大学でのキャンパス・研究室ツアーを通じて、STEM領域で活躍するロールモデルとの交流機会を提供しています。今年度、青山学院大学が財団の活動主旨に賛同し、本プログラムの参画大学として正式に加わったことを受け、今回のイベント実施に至りました。
【イベント開催報告】
当日は進路に悩んでいる、または理系に進もうと考え始めている26人の女子中高生とそのご家族25人の方が参加されました。相模原キャンパスD107教室において、黄晋二理工学部長、山田進太郎D&I財団 榊原華帆中高生事業担当から開会にあたり挨拶があり、STEM分野への進学を考えている女子中高生達に向けてエールが送られました。
続いて、諏訪牧子教授(理工学部 化学・生命科学科)の司会のもと「青学理工学部のリアル」と題して、多様な理系領域で学ぶ理工学部の学部生・大学院生11人の女子学生が登壇し、文理選択のエピソードや現在の研究内容をはじめ、学生生活での体験談、STEM分野で学ぶことの魅力や将来像などを具体的に紹介しました。
「元々理系科目が得意だった。」「高校時代に理系科目の成績はあまり良くなかった。文系科目の方が成績が良かったので、文理選択を迷った。しかし、やりたいことや興味があるのは理系分野だったため、苦しい選択だったが必死に勉強して理系に進んだ。」「小学校5、6年生のとき、先生に課された算数の難問を解いたとき、算数は公式や計算だけではない奥深さに気づいた。その際、時間をかけて考えてわかったときのうれしさが原動力になり、理系に進学した。」「高校の物理の女性教員に憧れて理系を目指した。」等、本学学生から興味深いエピソードが紹介されました。
また、「理工学部は女子学生の割合が少ない」ことや、「研究室でひたすら研究して、課題が多く自由な時間が少ない」というイメージを抱いていた学生もいましたが、「女子が少ないからこそ、女子同志の結束が強くなった。」「学びや研究以外にもやりたいことがあり、時間を調整してメリハリをつけることで、アルバイトや課外活動との両立ができたので楽しい学生生活が送れる。」等のアドバイスがありました。
そして一番多かったメッセージは、「好きなことをやってみよう!」でした。「やりたいことがあれば、多少不安で辛い壁に当たっても何とかなるし、楽しく続けられる。」とエールが送られました。
その後、中高生の参加者は3チームに分かれて研究室ツアーに向かいました。物理科学科の坂本貴紀教授(宇宙物理学、X線・ガンマ線天文学)、化学・生命科学科の平田普三教授(脳科学)、情報テクノロジー学科の伊藤雄一教授(ヒューマンコンピュータインタラクション)の研究室を見学しました。3研究室において、真剣な面持ちで本学学生による研究室紹介に耳を傾け、時にうなづきながら興味深く学生の取り組みを見学していました。また別途保護者の方々向けに、D106教室において、教職員による相談会を実施しました。
座談会「なんでも質問タイム」では、打ち解けた雰囲気の中、グループに分かれて、車座で女子学生とじっくりと意見交換の場が設けられました。
最後に、黄理工学部長から「本日はありがとうございました。今日のイベントが、参加者の皆さんの新たな気づきの一助となり、将来の具体的なイメージにつながる機会となれば幸いです。また本学を身近な存在に感じていただければ嬉しいです。これからも、皆さんが持つ「無限の可能性」を存分に広げてください。未来に皆さんとともに学び研究できることを楽しみにしています。」との挨拶があり、閉会となりました。