- MENU -
POSTED
2025.10.11
TITLE
【国際化推進機構】「ケンブリッジ・ファラデーセミナー」を開催 ~科学と信仰の対話をめぐって国際的視点から議論
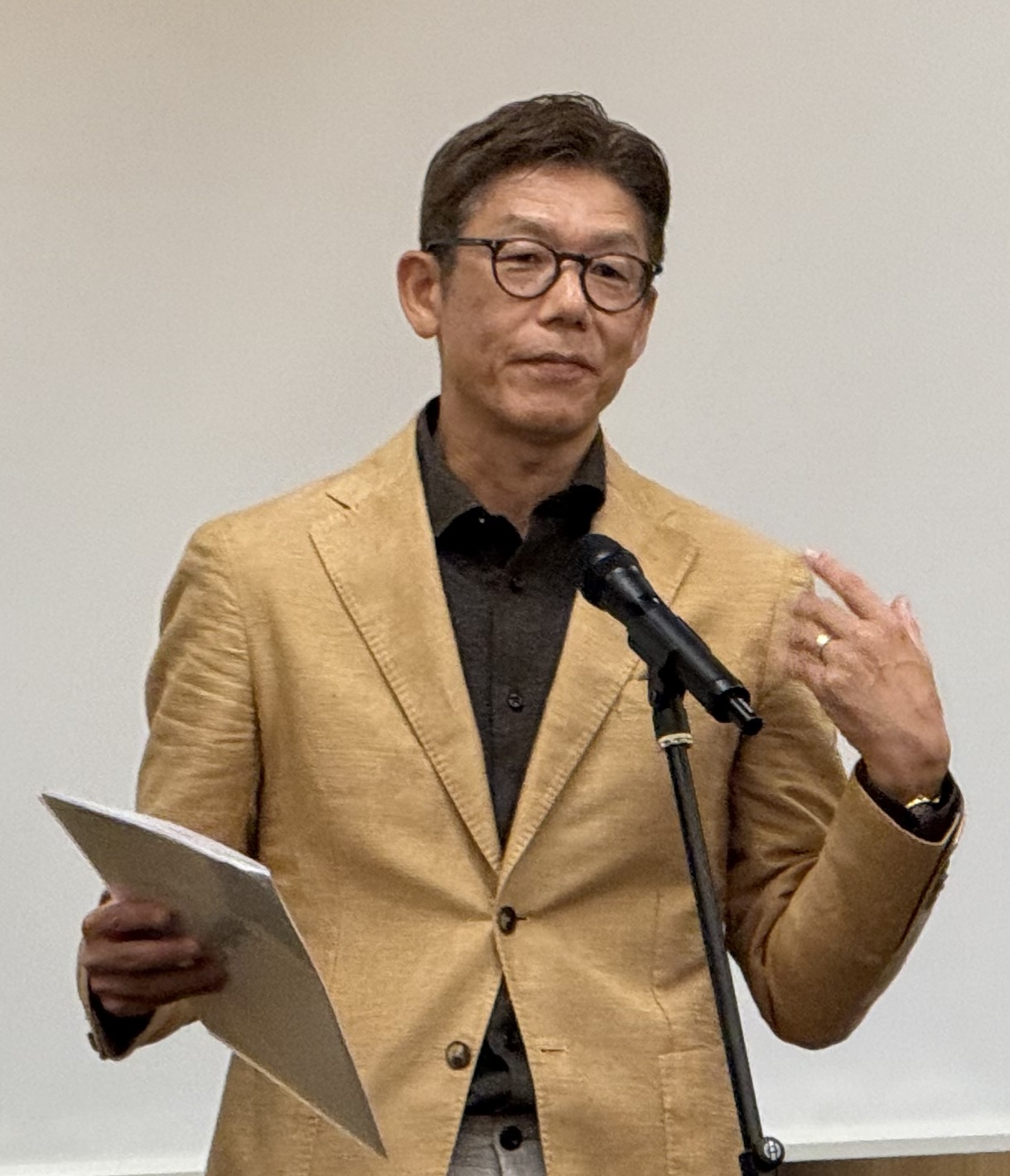 内田達也副学長の開会挨拶
内田達也副学長の開会挨拶
2025年9月22日(月)、青山学院大学 国際化推進機構は、ファラデーセミナー実行委員会主催が、大阪大学社会ソリューションイニシアティブ(SSI)および青山学院宗教センター共催のもと、青山キャンパス マクレイ記念館6階 プレゼンテーションルームにおいて、「ケンブリッジ・ファラデーセミナー」を、対面とオンラインのハイブリッド形式で開催しました。
本セミナーは、科学とキリスト教の関係について理解を深め、現代社会の課題を多角的に考えることを目的とし、科学と信仰というテーマは、「キリスト教にもとづく道徳的精神と科学的精神とを体得し、さらに英語の実際的訓練を受けた科学技術者を育成することで総合大学として研究と教育を充実させたい」とかつての理工学部設置認可申請時に、その申請書において述べている通り、まさに本学開催ならではといえるものでした。
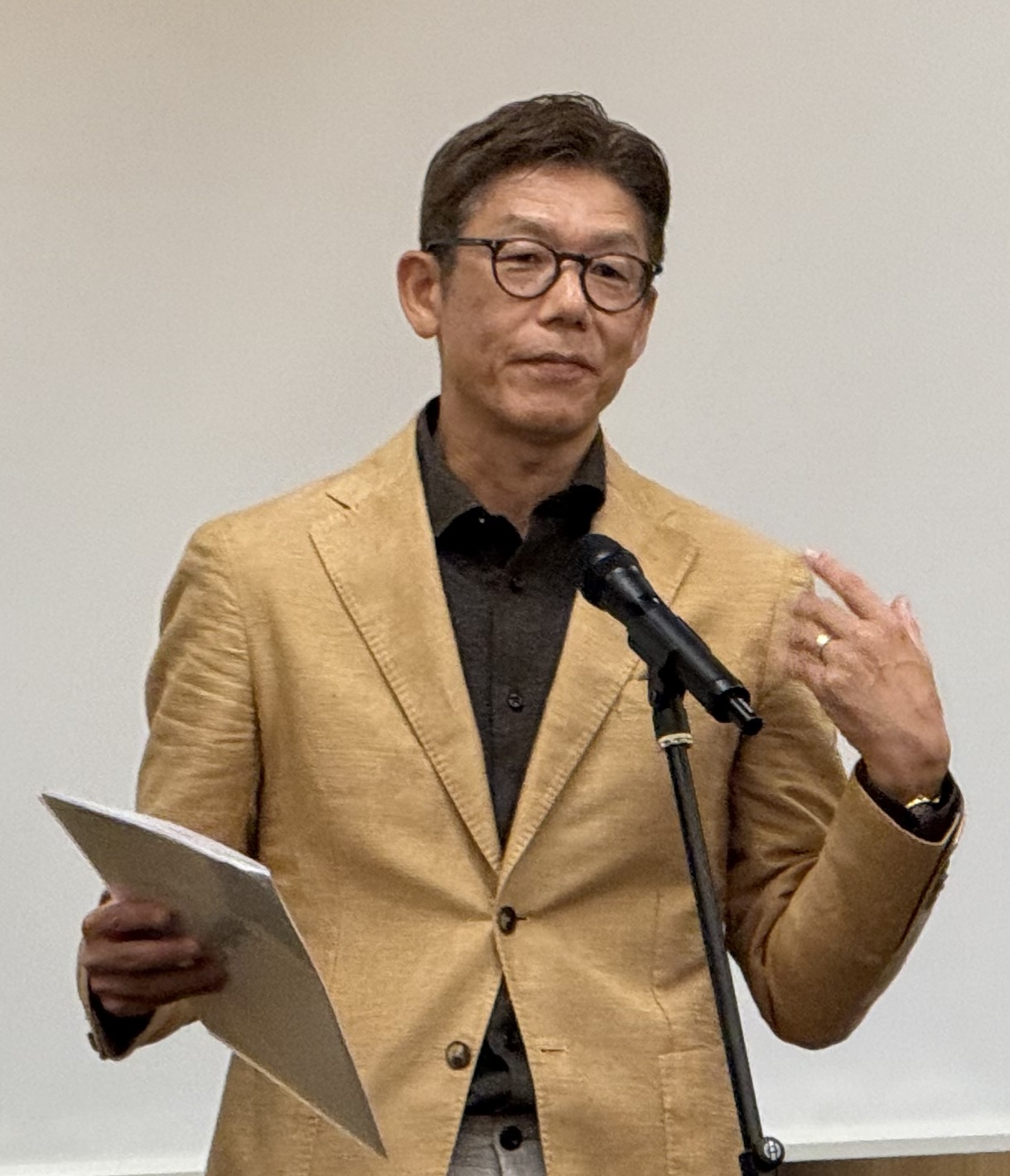 内田達也副学長の開会挨拶
内田達也副学長の開会挨拶 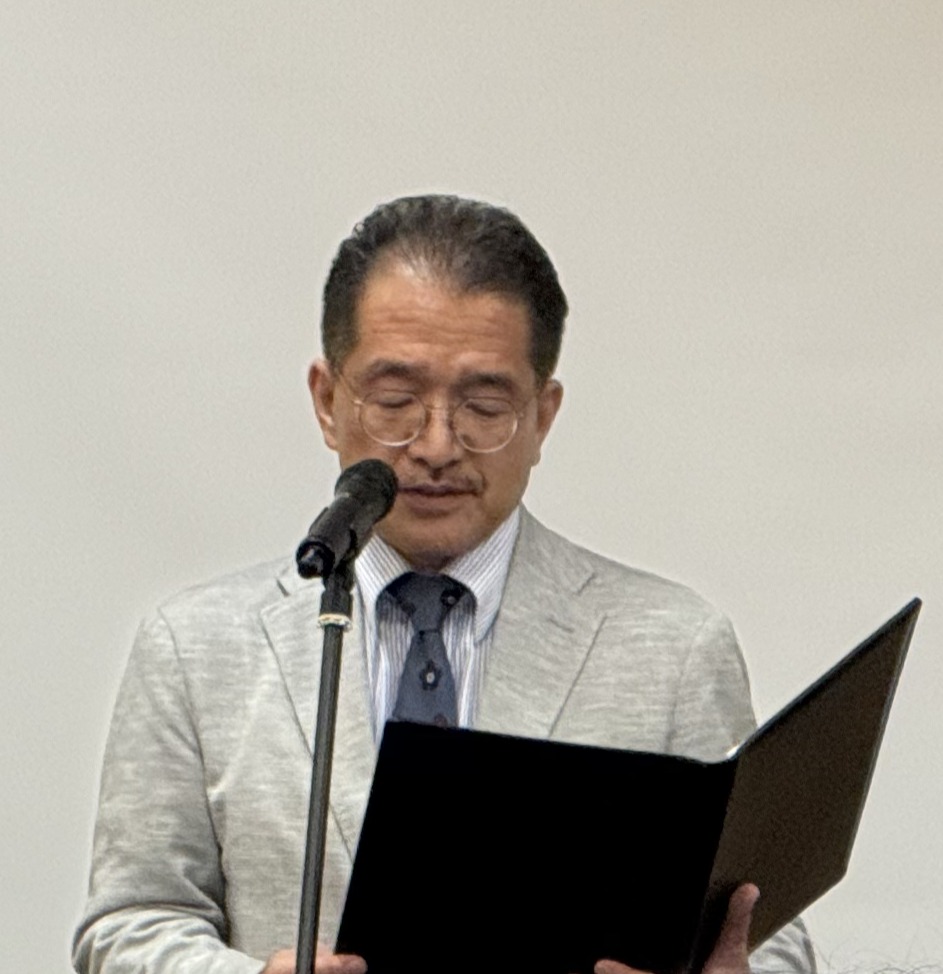 大宮謙大学宗教部長による開会祈祷
大宮謙大学宗教部長による開会祈祷 細井宏一(大阪大学・社会ソリューションイニシアティブ)招聘教授による司会のもと進行し、共催者を代表して内田達也副学長の開会挨拶、大宮謙大学宗教部長による開会祈祷の後、セミナーは始まりました。
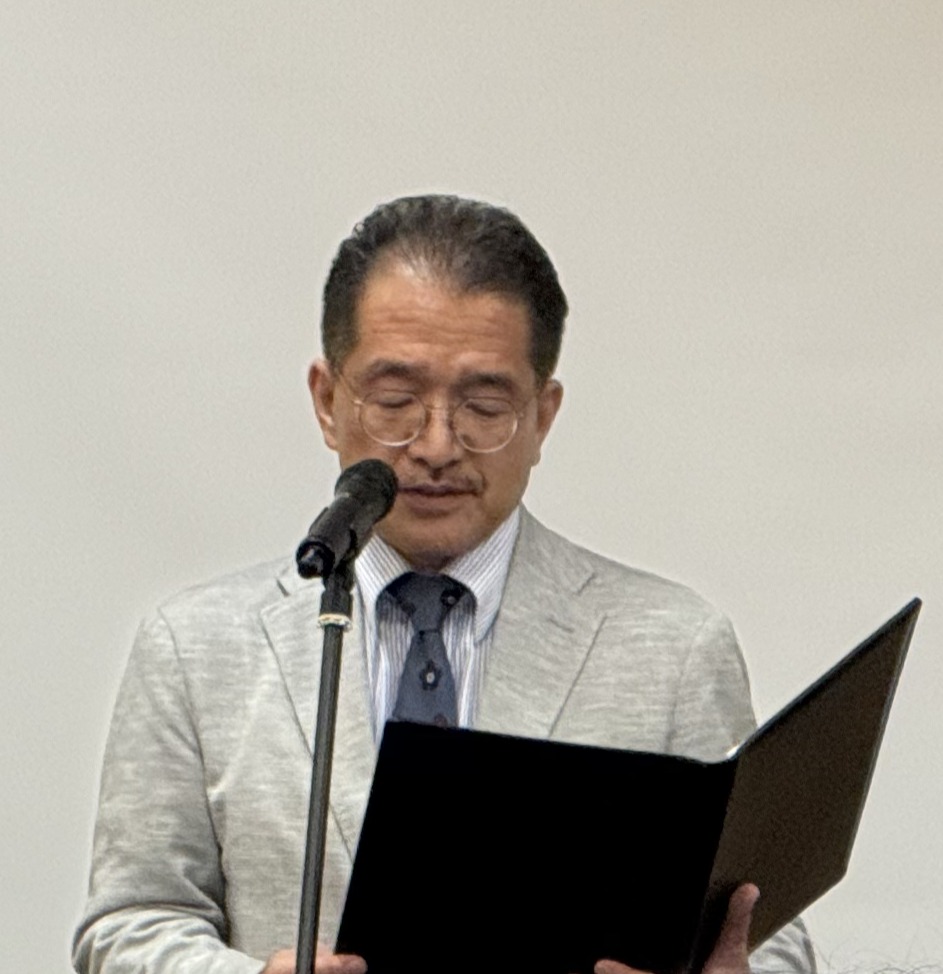 大宮謙大学宗教部長による開会祈祷
大宮謙大学宗教部長による開会祈祷  Graham Budd氏(ケンブリッジ大学ファラデー研究所)
Graham Budd氏(ケンブリッジ大学ファラデー研究所)
セミナー前半は、国内外の研究者による講演が行われました。
一人目の科学技術と宗教倫理の関係を専門とし、特にAIが社会に及ぼす影響を信仰的視点から分析しているGraham Budd氏(ケンブリッジ大学ファラデー研究所)からは、「AIと社会への影響を信仰の視点からどう理解するか」をテーマに、技術革新と倫理の交差点について語られました。
人工知能(AI)は、教育・医療・社会課題の解決など多くの分野で革新をもたらしています。一方で、国家間の技術競争や「汎用人工知能(AGI)」の追求が進む中、AIの本質に対する誤解も広がっています。AIに「意識」や「人格」があるとする見方は、技術の限界を見誤る危険性を孕んでいます。AIは膨大なデータを基に統計的に予測を行うものであり、人間のような理解力や倫理観をもつわけではありません。人間の知性は、身体性・関係性・創造性・道徳性といった要素に根ざしており、AIとは本質的に異なる存在です。
こうした違いを踏まえ、AIを「人間を凌駕する存在」としてではなく、「人間の繁栄を支援するツール」として捉えることが重要であり、医療画像の解析、災害リスクの予測、教育支援、異文化理解の促進など、AIは人間中心の設計によって社会に貢献する可能性を広げていると述べられました。
 Graham Budd氏(ケンブリッジ大学ファラデー研究所)
Graham Budd氏(ケンブリッジ大学ファラデー研究所)  Cara Parrett 氏(ケンブリッジ大学ファラデー研究所)
Cara Parrett 氏(ケンブリッジ大学ファラデー研究所)
二人目は神学と環境倫理の見地から、キリスト教の伝統が持つ「創造物への責任」の理念を基盤に、環境保護の新しい方向性を探求しているCara Parrett 氏(ケンブリッジ大学ファラデー研究所)からは、「環境保護とキリスト教的希望」をテーマに、環境危機と信仰・キリスト教から読み解く自然との関係性について語られました。
自然保護活動の現場では、文化的・精神的・倫理的価値観が人々の行動に強く影響することが認識されつつあり、宗教的世界観との対話が重要なテーマとなっています。特にキリスト教の聖書的視点から、人間と自然との関係性を読み解くと、聖書では、すべての被造物は神によって創造され、神に属するものであるとされ、人間はその「世話役」として、思いやりと責任をもって自然を管理するよう求められています。
自然は神の創造物として固有の価値を持ち、その美しさと秩序は創造主への賛美とされます。また、聖書の中心的な教えである「神と隣人への愛」は、環境破壊によって最も影響を受ける貧困層や弱者への配慮を促す倫理的動機となります。多くのキリスト教徒の自然保護活動家は、信仰を支えに活動を続けており、神の回復の業に参与するという希望が、困難な状況でも粘り強さを与えているのです。この講演が、環境問題に対する宗教的・倫理的アプローチの可能性を示すとともに、信念や価値観が環境保護の実践において果たす役割を再考する機会となることを願っており、多様な視点に耳を傾けることで、共感と協力の精神に基づいた持続可能な社会の構築が可能になると述べられました。
 Cara Parrett 氏(ケンブリッジ大学ファラデー研究所)
Cara Parrett 氏(ケンブリッジ大学ファラデー研究所)  堂目卓生氏(大阪大学総長補佐・社会ソリューションイニシアティブ長)
堂目卓生氏(大阪大学総長補佐・社会ソリューションイニシアティブ長)
三人目は、専門の経済思想史の見地から「いのち」を中心に据えた社会を提唱し、市民と研究者が協働する「いのち会議」を推進している堂目卓生氏(大阪大学総長補佐・社会ソリューションイニシアティブ長)。「共助社会を目指して - いのちフォーラムの理念と実践」というテーマで、共助社会の実現に向けた新たな挑戦について語られました。
新型コロナウイルス感染症や自然災害などを通じて、誰もが「助けを必要とする人」になり得ることが明らかになりました。そして、助けられた経験が新たな行動や力を引き出し、他者を支える原動力となることもあります。大阪大学は2023年、関西経済連合会、大阪商工会議所、関西経済同友会と連携し、「いのち会議」を発足しました。この取り組みは、災害や気候変動、社会的格差など、現代社会が直面する多様な課題に対し、「共助社会」の構築を目指すものです。「共助社会」とは、助けを必要とする“いのち”を社会の中心に据え、その周囲を助ける“いのち”が取り囲み、互いに支え合う社会のあり方です。ここでいう“いのち”とは、人間だけでなく、動植物や自然、地球そのものを含む広い概念であり、その尊厳や可能性を重んじる姿勢が根底にあります。助ける”いのち”と助けられる”いのち”の関係は一方向ではなく、双方向的であり、そして流動的です。
「いのち会議」は「誰一人取り残さない」というSDGsの理念や、「いのち輝く未来社会のデザイン」を掲げる大阪・関西万博と連動しながら、持続可能で包摂的な社会の実現に向けた実践的なモデルの提示について述べられました。
 堂目卓生氏(大阪大学総長補佐・社会ソリューションイニシアティブ長)
堂目卓生氏(大阪大学総長補佐・社会ソリューションイニシアティブ長)  細井宏一氏(大阪大学・社会ソリューションイニシアティブ招聘教授)
細井宏一氏(大阪大学・社会ソリューションイニシアティブ招聘教授)
そして最後に、社会システムデザインや文化政策を専門とし、循環型経済のあり方を「接合と分離」の観点から研究している細井宏一氏(大阪大学・社会ソリューションイニシアティブ招聘教授)からは、「循環型経済の創造」と題し、科学技術と倫理の融合:Society 5.0の実現に向けて、「接合と分離」の統合化技術の可能性について発題がありました。
大阪大学では、未来社会の設計に向けた新たな視点として、「接合と分離の統合化技術」に注目しています。この技術は、単なる道具としての技術を超え、人間と世界との関係性を再構築する媒体(メディア)として位置づけられています。そこには、科学技術と倫理、さらには神学的な問いをも含む、総合的な対話の可能性が広がっています。
この技術は、循環型経済の中核を担うものとして、Society 5.0の実現に向けた重要な役割を果たします。大いなる絶対的価値に基づいて、理工学などの自然科学、経済学などの社会科学、そして倫理学や神学といった人文科学の3種類の科学分野を統合した視点から、技術革新だけでなく、制度設計や価値観の再構築を連鎖的に促進していくことが期待されています。
そこでは、新たな技術開発に加えて、倫理的な心理面や行政・政策面からの支援を含めた社会全体のパラダイム転換が求められています。こうした持続可能で包摂的な社会の構築に向けた実践的なアプローチは、今後の研究・教育・政策形成において重要な手がかりとなるでしょう。
このように、「接合と分離の統合化技術」は、未来社会の設計において、科学と人文の境界を越えた学際的な対話を促進する鍵となる技術です。Society 5.0の理念を具体化するソリューションとして、循環型経済の実現に向けた取組みの中で、今後、大いに注目される革新的な技術分野であると述べられました。
 細井宏一氏(大阪大学・社会ソリューションイニシアティブ招聘教授)
細井宏一氏(大阪大学・社会ソリューションイニシアティブ招聘教授)  セミナー後半のパネルディスカッション
セミナー後半のパネルディスカッション 後半のパネルディスカッションでは、青山学院大学・大阪大学・ファラデー研究所の研究者が登壇し、科学と宗教の対話が社会に果たす役割について議論しました。前半の講演会登壇者に加えて、本学から小松靖彦教授(文学部 日本文学科)、左近豊教授(大学宗教主任・国際政治経済学部)、水山元教授(理工学部 経営システム工学科)が参加し、幅広い専門領域から活発な意見交換が行われました。
 セミナー後半のパネルディスカッション
セミナー後半のパネルディスカッション
最後にこのセミナーを結ぶにあたって、主催者を代表してファラデーセミナー実行委員会の細井宏一氏による閉会挨拶があり、盛会のうちに終了しました。
本セミナーは、研究者や学生・教職員にとって「科学と信仰」という一見相反するテーマを、国際的かつ学際的に考察する貴重な機会となりました。参加者からは、「濃い内容で、講演時間が短く感じられた」「英語での議論を通じて視野が広がった」「環境やAIの問題を宗教的観点から考える新しい視点を得た」「それぞれの専門分野と宗教や倫理の関係、科学が発展するうえでどのように宗教や人間たる部分がかかわっていくか、これから地球全体がどのように共生していったらよいかを、それぞれの立場から意見が聞けてとても興味深かった」「講演の内容をすこし深堀した意見も聞けて良かったと思う」といった感想が寄せられました。
青山学院大学は今後も、国際的な学術交流を推進し、多角的な学びの場を提供していきます。本報告はシンポジウム登壇者の発表資料を基に作成しました。作成にあたり、細井先生には多大なご協力をいただきました。





