- ホーム 学外講座(イベント) 【青山キャンパス公開講座】ジェンダーと表現
EVENT(学外講座)
- MENU -
SCHEDULED
2024.11.09 - 2024.12.14
TITLE
【青山キャンパス公開講座】ジェンダーと表現
講座概要
対面またはオンライン配信
2024/11/09 ~ 12/14 毎土曜日 11:00~12:30(初回のみ12:40)
表現することは人間の自己意識の基本であり、表現行為および表現されたものには、ジェンダーの問題、その社会背景が強く反映されます。文学、美術、音楽といった表現ジャンル、歴史の中で、ジェンダーの問題がどのように扱われてきたのか、表現者たちがどう取り組んできたのかを学び、考えます。
第1回 2024/11/09(土)絵本・児童文学の中のジェンダー
コミュニティ人間科学部コミュニティ人間科学科 准教授
西山 利佳[Nishiyama Rika]
ジェンダーはおとなになって意識的に身に着ける概念ではなく、成長の過程で身の回りのあらゆるものから影響され、いつのまにか刷り込まれてしまうものです。身近なおとなの言動に始まり、子どもたちをとりまくあらゆるものが陰に陽に「女の子らしさ」「男の子らしさ」を発信していると言えるでしょう。子どもたちをとりまく環境の一つであり、身近な表現物である絵本や児童文学をジェンダーの観点で見直すことは、おもしろいだけでなく重要なことだと考えています。
まずは、作者が意識してか無意識でか、作中に込めてしまったジェンダーバイアスをいくつかの絵本で見ていきたいと思います。次に、ジェンダーからの解放を意図して作られた作品を中心に、近年の作品を紹介し、無意識に潜むジェンダー観を自覚し、そこからの解放をめざすことがなぜ求められるのか、腑に落ちるお話ができたらと考えています。
<プロフィール>
青山学院大学 コミュニティ人間科学部コミュニティ人間科学科 准教授
西山 利佳 [Nishiyama Rika]
1961年、宮崎県生まれ。都留文科大学文学部国文科卒。東京学芸大学修士課程修了。2016年~2021年、青山学院女子短期大学子ども学科准教授。日本児童文学者協会常任理事。日本ペンクラブ「子どもの本」委員会副委員長。日本児童文学学会ほか会員。評論集『〈共感〉の現場検証 児童文学の読みを読む』(くろしお出版、2011年)、共編著『わたしたちのアジア・太平洋戦争』(全三巻、童心社、2004年)ほか。2024年1月より、月刊雑誌『クレスコ』(大月書店)に、「先生読んで! おとなのための児童文学案内」を連載中。
第2回 2024/11/16(土)美術を見ること、つくることとジェンダー
青山学院大学 東京神学大学 東京外国語大学 非常勤講師
眞下 弥生[MASHIMO Yayoi]
美術館は往々にして、卓越した造形芸術表現/美術を展示、鑑賞する場だと考えられています。では、刺繍や編み物のような「手芸」は、美術に含まれるでしょうか。主に女性の手による余暇的なもの、副業の一環、美術館のような施設が収集・展示する対象にはならない格の低いものというイメージが先に立つかもしれません。一方、そのようなイメージを逆手に取り、「手芸」の手法で美術の制度や社会のあり方に問いを投げかける表現も数多くあります。
また、講師は美術鑑賞や制作のワークショップを行なっていますが、技法を体験する、鑑賞した作品を元に自分も何かを作るなど、実際に手を動かしてみることを大切にしています。そうした中、パレスチナの女性たちが作ってきた刺繍にまつわるワークショップを企画した際、さまざまな課題に直面しました。その経験も併せてお話ししたいと思います。
<プロフィール>
青山学院大学 東京神学大学 東京外国語大学 非常勤講師
眞下 弥生[MASHIMO Yayoi]
ジョージ・ワシントン大学教育学大学院修士課程博物館教育専攻修了。校正・翻訳の仕事をしながら、美術鑑賞・制作のワークショップを行なっている。共著に『ふれる世界の名画集』(日本点字図書館)、翻訳に『たどりつくまで』(新教出版社)。青山学院大学では、青山スタンダード科目「キリスト教美術」を担当。
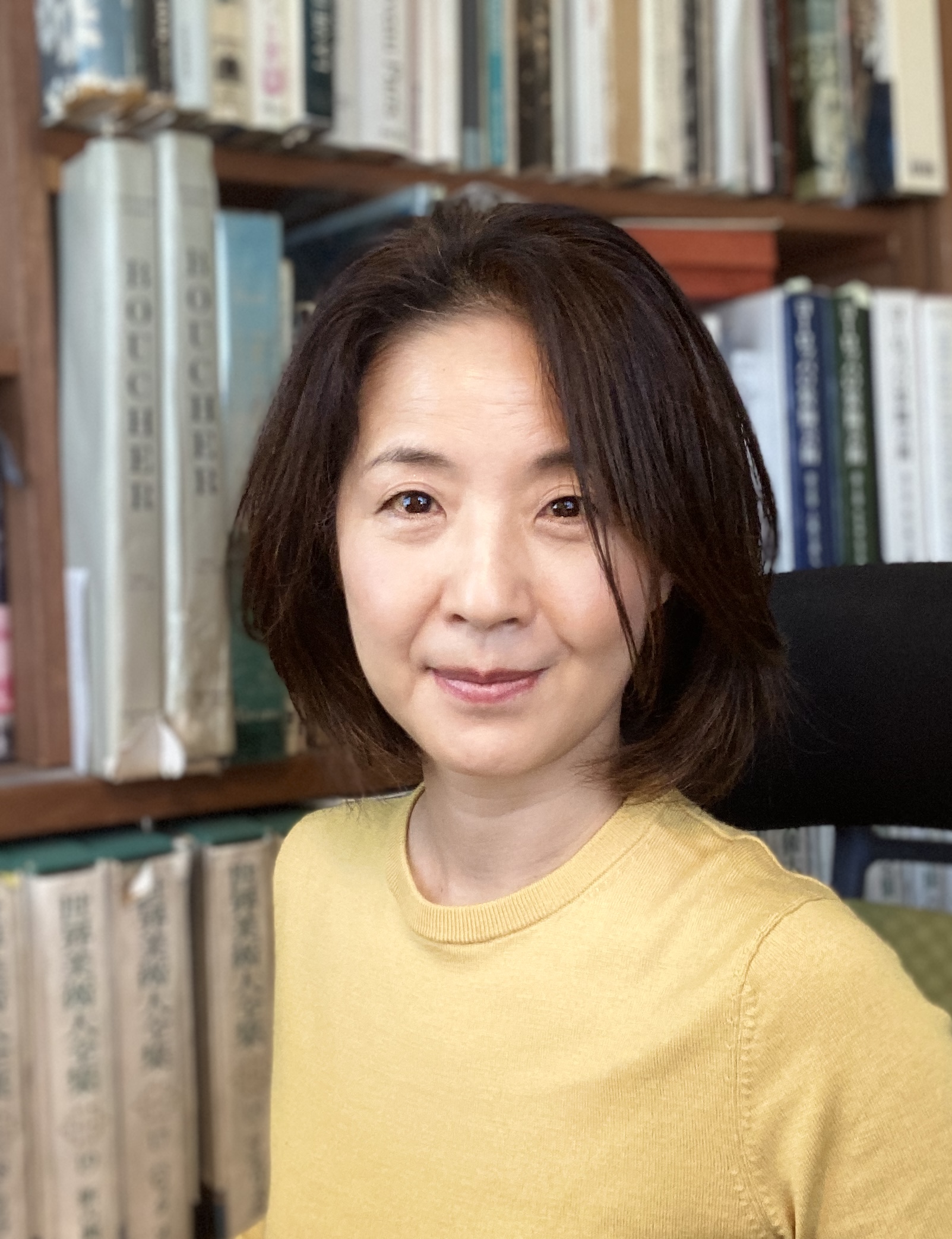
第3回 2024/11/30(土)版画と女性
日本大学 非常勤講師
伊藤 已令 [ITO Mirei]
近年、女性版画家の活躍を再評価する動きがある。
版画は、14世期後半、東洋から木版画としてヨーロッパに伝わったが、ルネサンスになると、独自の技法である銅版画が発明された。より精密な線をもつ銅版画は、人々の知識欲を満たし、図像を伝達し、楽しみを与えるものとして飛躍的に発展し、社会的に重要な役割を担うようになる。
16世紀になると多くの企業化された工房が生まれた。進取の気性のある版元が原画を見出し、そこに下絵師、彫り師、刷り師が集められ、世界をまたにかけた販売網が築かれた。この過程に女性も参画した。彫版の腕をたよりに版元となった女性、父の出版事業を助ける妻や娘、夫亡き後事業を継承し企画や販売を手掛ける未亡人など、版画の制作現場で女性がいかに活躍したかを知ることは意味があるだろう。
今回は、版画史のなかの女性の活動にスポットライトをあて、作品をまじえながら具体的にお話しをしたいと思う。
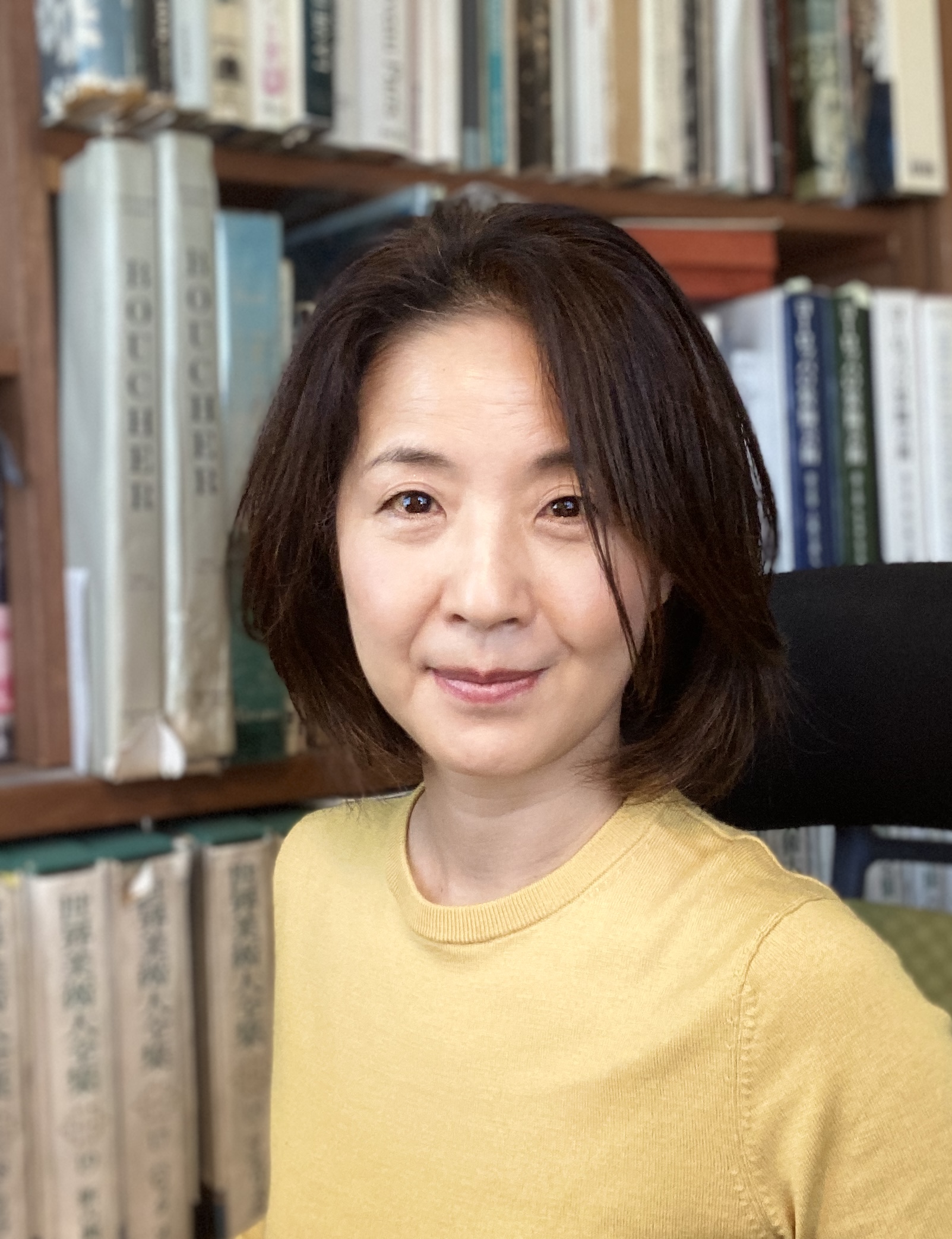
<プロフィール>
日本大学 非常勤講師
伊藤 已令 [ITO Mirei]
日本大学文理学部非常勤講師。お茶の水女子大学卒業、お茶の水女子大学人間文化研究科単位取得退学、博士(人文科学)。日本学術振興会特別研究員を経て、明治学院大学、青山学院女子短期大学、日本大学などで教える。 専門は18世紀フランス美術史、版画史。共著『世界美術大全集 第18巻』(小学館、1996)、『フランス近世美術叢書Ⅳ 絵画と表象Ⅰ』(ありな書房、2015)等。
第4回 2024/12/07(土)日本における初期讃美歌集と女性
教育人間科学部 教授
山本 美紀[YAMAMOTO Miki]
賛美歌の歴史を「女性」という切り口から考えるにあたって、本公開講座では、『譜附・基督教聖歌集』(1884, 明治17年版)に関わり、青山学院と関係が深く、日本の初期賛美歌集と女性の歴史を語る際には外せない永井ゑい子(1866-1926)と、子供のための賛美歌の歴史に大きな足跡を残した『ゆきひら』(1901, 明治34年)の著者、武良温クララ(Clara L. Brown1864-1911)と、歌集編纂のきっかけとなった安田靖子(生年不明-1925)をとりあげます。
当時の事情では、歌集に彼女たちの名前が残るか残らないかは、夫をはじめ周りの男性がなにがしかの記録を積極的に残していない限り、どんなに活発な活動をしていても後世に伝わることはほとんど期待できません。
本講座では、そのような賛美歌研究の一面を紹介しつつ、彼女たちの生き生きとした賛美歌翻訳/創作への関わりについてお話をしたいと思います。

<プロフィール>
青山学院大学 教育人間科学部 教授
山本 美紀[YAMAMOTO Miki]
青山学院大学教育人間科学部教授。ウィーン市立音楽院を経て、大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了(博士(文学))。専門は音楽学・音楽教育学。現在、青山学院大学総合研究所研究ユニットでは、ユニットリーダーとして青山学院所蔵「〔賛美歌作家〕津川主一コレクション」のデジタルアーカイブ化と分析に取り組むかたわら、神奈川県立音楽堂と共に文化施設の芸術教育プログラムについて研究を進めている。
2024年11月15日に発売予定の『新しい音楽が息づくとき』(井手口彰典,山本美紀編著,春秋社)では、「第3章 新しい歌の生まれる時 ――由木康と津川主一による子供のための賛美歌創作」を執筆。また単著に『メソディストの音楽 : 福音派讃美歌の源流と私たちの讃美』(ヨベル、2012)、『音楽祭の戦後史 : 結社とサロンをめぐる物語』(白水社、2015)、他。
日本賛美歌学会副会長、日本ウェスレー・メソジスト学会会長。

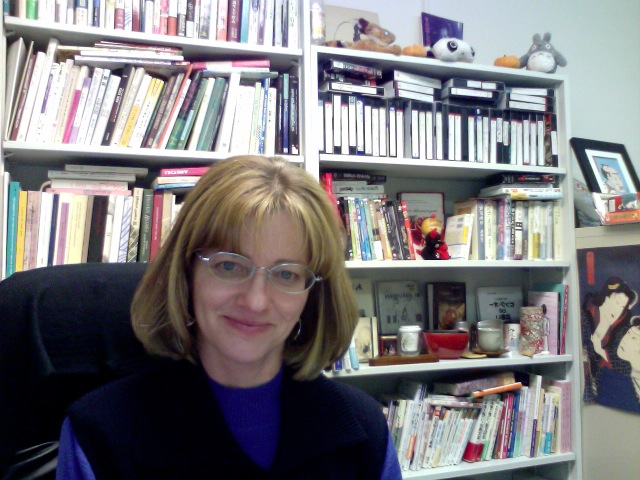
第5回 2024/12/14(土)文学における戦争とジェンダー
文学部英米文学部 教授
メアリー・ナイトン[Mary A. KNIGHTON]
古くから戦争文学と考えると、男性中心的な世界の歴史の記録、あるいは冒険譚、と直ぐに思い浮かぶだろう。厳しい戦場で自分の男らしさが試され、最終的には洗練されたヒーローの地位にまで達することが可能な物語。戦争文学において、人間性の代表者としての男性主人公が、勝っても敗れてもロマン主義的な道を辿ることが多い。女性の表象というと、戦争文学の中では大抵守らなくてならない存在であり、何よりも国と家族に連想される。彼女たちは戦争の背景や周縁地以外ではあまり目立つことがない。戦争が生死の現場であるからこそ、ジェンダーと表現は極端な状態となる。戦争文学におけるジェンダーへの挑戦、そしてその問いかけから、何が見えてくるだろうか。
本講座ではアメリカ文学と日本文学から、ジェンダーと人類と社会経済階級の交差する文学作品を中心に具体的な例を取り上げ、ジェンダーと表現の意味合いを探りたい。
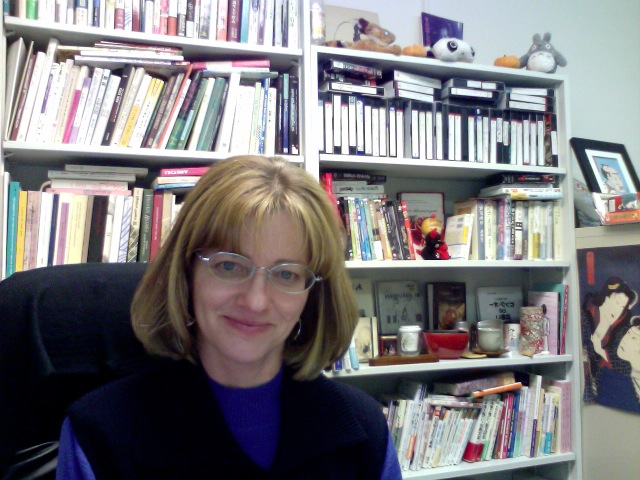
<プロフィール>
青山学院大学 文学部英米文学部 教授
メアリー・ナイトン[Mary A. KNIGHTON]
メアリー・A.ナイトンは近現代アメリカと日本の文学文化の研究者である。カリフォルニア州立大学バークレー校博士課程修了。アメリカ南部の作家のウィリアム・フォークナーの作品について博士号を取得後、講師・准教授としてアメリカと日本にある大学への所属を経て、2015年から青山学院大学の英米文学科に勤務。
論文に、“Toddler-Hunting in Wartime: Kōno Taeko’s ‘On the Inside’,” Japanese Language and Literature Vol. 56, No. 2 (2022)(戦時中の幼児狩り:河野多恵子の「塀の中」、未訳);「昆虫文学」―その底なしの魅力『学術の動向』編集協力、日本学術会議(令和3年第26巻第4号 (“The Endless Fascination of Insect Literature,” Trends in the Sciences (Science Council of Japan)(Vol.26, April 2021)、など。
講座申し込み
お申し込み時に受講形式(対面またはオンライン)をお選びください。講座の途中で変更することはできません。
CONTACT
-
お問い合わせ先
青山学院大学社会連携部社会連携課
〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25
-
TEL / MAIL
03-3409-6366
-
受付時間
月~金 9:00~17:00 (事務取扱休止 11:30~12:30)