- ホーム 学外講座(イベント) 【青山キャンパス公開講座】渋谷で中世! ~東京の都心で中世に触れる~
EVENT(学外講座)
- MENU -
SCHEDULED
2025.05.10 - 2025.06.07
TITLE
【青山キャンパス公開講座】渋谷で中世! ~東京の都心で中世に触れる~
講座概要
対面またはオンライン配信
2025/05/10~ 06/07 毎土曜日 11:00~12:30(初回のみ12:40)
渋谷は東京を代表する繁華街として有名ですが、同時に、様々な大学や博物館・美術館が集まるなど、意外にも(?)人文研究が盛んな街でもあります。
本講座では、渋谷にある大学が協力し、個別の学部学科を超えて、日本の中世という時代に光を当ててみたいと思います。
中世は現代と同様、混迷の時代ではありますが、そこから多彩な文化が花開いた時代でもありました。歴史、文学、芸術、宗教など多様な角度から中世的世界を覗いてみましょう。
第1回 2025/05/10(土)『太平記』の虚像と実像 ―日本中世史研究の現在地―
文学部 准教授
谷口 雄太[TANIGUCHI Yuta]
第1回は歴史学です。日本史、とりわけ中世史を舞台に、研究の現在地の一端を紹介します。今回扱うのは14世紀の南北朝時代。近年、『逃げ上手の若君』というマンガ・アニメが大ヒットしていて、若者を中心に関心が広まってきています。その南北朝を描いた文学作品(軍記物語)に『太平記』があることはよく知られているでしょう。しかし、『太平記』は史実をベースとしながらも、あくまでフィクションでありますから、どこまでが事実であり、どこからが虚構なのかは、きちんと腑分けしなくてはなりません。そこで、本講義では、新田義貞という人物に注目し、彼の虚像と実像について見ていきます。新田義貞を、足利尊氏とは別の一族で、彼と並ぶ源家嫡流であったとする『太平記』のストーリーに対して、リアルな彼の姿を紹介します。すなわち、「源家嫡流」などではなく、「足利庶流」(足利一門)であった新田義貞。こうした驚くべき事実が浮かび上がってくることになるでしょう。あわせて、史実を明らかにしていく歴史学の手法・方法についても紹介します。
<プロフィール>
青山学院大学文学部史学科 准教授
谷口 雄太[TANIGUCHI Yuta]
1984年、兵庫県生まれ。2015年、東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得満期退学。現在、青山学院大学文学部准教授、博士(文学)。
【主要著書】『中世足利氏の血統と権威』(吉川弘文館、2019年)、『〈武家の王〉足利氏』(吉川弘文館、2021年)、『分裂と統合で読む日本中世史』(山川出版社、2021年)、『足利将軍と御三家』(吉川弘文館、2022年)、『鎌倉幕府と室町幕府』(共著、光文社、2022年)、『足利一門と動乱の東海』(編著、吉川弘文館、2024年)
第2回 2025/05/17(土)聖地・熊野の中世 ―紀伊半島を見はるかす―
実践女子大学文学部国文学科 教授
大橋 直義[OOHASHI Naoyoshi]
2004年7月に「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産に登録されてから20年あまりが経ちました。そこでは、熊野、吉野大峯、高野山、およびそれらを繋ぐ参詣道と共に、紀伊半島の貴重な文化遺産として位置づけられています。
この講義で主に取り上げるのは、熊野本宮大社、熊野速玉大社(新宮)、熊野那智大社および青岸渡寺から成る熊野三山です。平安時代後期以後、上皇・法皇ら時の為政者たちは廷臣らと共に聖地熊野を目指しましたが、そもそもそれは何のためになされたことだったのでしょうか。同じ時期、平清盛ら平家一門もやはり熊野をたびたび訪れていますが、聖なる空間としての熊野がいつごろからいかにして形成され、そして熊野参詣や西国三十三箇所巡礼の起点としてイメージされるようになっていったかについて、様々な文化財の画像と共に考えてみます。

<プロフィール>
実践女子大学文学部国文学科 教授
大橋 直義[OOHASHI Naoyoshi]
1973年生。京都府出身。
博士(文学・慶應義塾大学)。
慶應義塾大学文学部、同大学院文学研究科国文学専攻、日本学術振興会特別研究員(DC2およびPD)を経て、和歌山大学教育学部准教授。2021年度より実践女子大学文学部国文学科教授。専門は日本中世文学。日本中世の歴史叙述とその書物。巡礼・参詣の史的研究。地域史研究と文化財(殊に古典籍・聖教)研究の架橋。趣味は展覧会鑑賞と古典籍蒐集。
主な著書に『転形期の歴史叙述―縁起 巡礼、その空間と物語―』(慶應義塾大学出版会、2010)。編著に『中世寺社の空間・テクスト・技芸―「寺社圏」のパースペクティヴ―』(共編、勉誠出版、2014)、『根来寺と延慶本『平家物語』―紀州地域の寺院空間と書物・言説―』(勉誠出版、2017)。

第3回 2025/05/24(土)中世武蔵野の和歌と連歌
文学部 教授
山本 啓介 [YAMAMOTO Keisuke]
武蔵野は古く『万葉集』の東歌に詠まれ、『古今和歌集』の「紫のひともとゆゑに武蔵野の草はみながらあはれとぞ見る」(雑上・読み人知らず)は特に著名で、『源氏物語』にも影響を与えた。以後の和歌でも少なからず詠まれ続けた。しかし、この時代に詠まれた武蔵野は、ほとんどが都の貴族達があくまでイメージだけで詠んだ、いわゆる歌枕としてであった。時代が下って中世となり、関東の重要性が増し、さらに戦乱の時代に入ると、武蔵野がより現実感を伴って文学作品に現れてくる。歌人や連歌師は様々な理由で武蔵野を旅し、現地を実見しながら和歌・連歌を詠んだ。それらの作品を中心に『とはずがたり』『太平記』『武蔵野紀行』などの散文作品も適宜取り上げながら、江戸幕府が開かれる以前の、中世の武蔵野の風景を紐解く。

<プロフィール>
青山学院大学 文学部日本文学科 教授
山本 啓介 [YAMAMOTO Keisuke]
青山学院大学文学部博士課程修了。新潟大学教育学部准教授、青山学院大学准教授を経て、2021年より同大学教授。専門分野は中世和歌・連歌。著書に『詠歌としての和歌』(新典社・2009年)、『歌枕の聖地 和歌の浦と玉津島』(平凡社、2018年)など。

第4回 2025/05/31(土)『源氏物語』はどのように読まれたか?
実践女子大学文学部国文学科 教授
舟見 一哉[FUNAMI Kazuya]
平安時代につくられた『源氏物語』は、現代に至るまで世界中で愛されている世界文学のひとつです。ただし、つくられた当初から現在まで、ずっと同じように読まれてきたか(内容を理解されてきたか)というと、そうではありません。例えば、読むために使う本文は、時代や地域などによって異なっていましたから、どの『源氏物語』を読むかによって、理解も異なります。『源氏物語』は、様々なかたちや大きさの写本に多様な筆跡で書写されてきましたので、モノとしても変化を繰り返してきました。また物語とは異なるメディアへと変形していくこともありました。本講義では、中世という時代を中心にしながら、『源氏物語』の本文・写本・解釈・変形をキーワードに、『源氏物語』はどのように読まれたのか概観します。
<プロフィール>
実践女子大学文学部国文学科 教授
舟見 一哉[FUNAMI Kazuya]
京都大学大学院博士課程修了。文学(博士)。専門分野は中古中世日本古典文学・日本古典籍書誌学。主な業績は、「和歌集のTEI準拠テキストデータに対する期待と要望」(『武蔵野⽂学』72号、2024)、「実践女子大学蔵『紫式部集』は長珊筆か」(『紫式部集の世界』勉誠出版、2023)、「『源氏物語』の引歌と『古今集』―主として墨滅歌をめぐる疑義と提言」(『ひらかれる源氏物語』勉誠出版、2017)など。
第5回 2025/06/07(土)異形の神:荼吉尼天―中世神仏習合の世界―
文学部 教授
津田 徹英[TSUDA Tetsuei]
周知の通り、日本の稲荷信仰は中世以来、神道系と仏教系に大きく分かれる。この講義では後者にかかわる中世の多様な造形を総覧する。あわせて、これにかかわる「即位灌頂」の本尊の姿かたちについて及んでみたい。この「即位灌頂」とは、中世において歴代の天皇が即位のため、最初に玉座のある高御座(たかみくら)に登壇する際に、人知れず大日如来の智拳印を結び、荼吉尼天の真言を唱える「秘儀」を指す。この秘儀についての研究は、歴史学、国文学、思想史、神道史の分野からの研究蓄積がある。にもかかわらず、それに関わって観念・祈念されていたであろう荼吉尼天の姿かたちについてはこれまで全く浮かび上がってこなかった。この講義ではこれに関わると思われる荼吉尼天図(14世紀)について、実査にもとづく所見を述べてみたい。
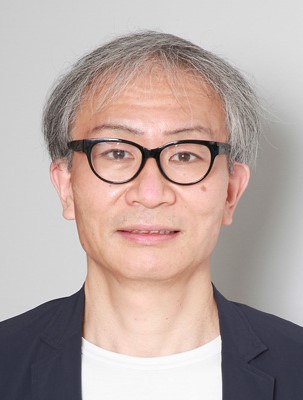
<プロフィール>
青山学院大学文学部比較芸術学科 教授
津田 徹英[TSUDA Tetsuei]
1963年生まれ。慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程単位取得済退学。博士(美学)。専門は日本彫刻史・密教図像学。神奈川県立金沢文庫学芸員、国立文化財機構東京文化財研究所文化財情報資料部長を経て、2018年から現職に。研究対象と関心は、東アジアの文物交流を見据えつつ、奈良時代から平安時代(8~12世紀)に及ぶ密教彫刻とそれにかかわる文化事象を研 究の中心に据えている。さらに、鎌倉・南北朝時代(13~14世紀)の異形の神像と肖像(彫刻・絵画)、絵巻物の研究にも及んでいる。単著に『中世の童子形(日本の美術442)』(至文堂、2003年)、『平安密教彫刻論』(中央公論美術出版、2016年)、編著に『組織論―制作した人々(仏教美術論集)』(竹林舎、2016年)、共著に『アジア仏教美術論集:東アジアⅦ(アジアの中の日本)』(中央公論美術出版、2023年)ほか多数。
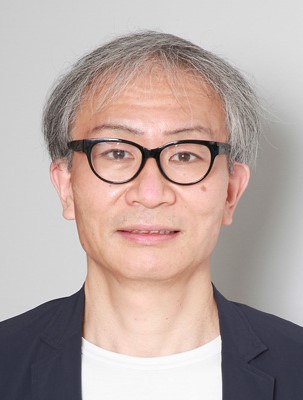
講座申し込み
お申し込み時に受講形式(対面またはオンライン)をお選びください。講座の途中で変更することはできません。
CONTACT
-
お問い合わせ先
青山学院大学社会連携部社会連携課
〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25
-
TEL / MAIL
03-3409-6366
-
受付時間
月~金 9:00~17:00 (事務取扱休止 11:30~12:30)