統計データサイエンス学環(構想中)の教員と企業のトップランナーとの対談を通じ、統計・データサイエンスの可能性について考える本企画。第一回目は、本学理工学部出身であり『じゃらん』や「ホットペッパービューティー」など数々のサービスを指揮してきた株式会社リクルート取締役会議長北村吉弘氏と、新学環開設準備室室長荒木万寿夫教授が、激変する時代に統計データサイエンスを学ぶ意義について語り合いました。前編では、統計データサイエンス学環(構想中)の設置の背景と、社会で求められるデータサイエンス人材の姿に迫ります。
PROFILE

株式会社リクルート
取締役会議長
北村 吉弘
KITAMURA Yoshihiro
1997年青山学院大学理工学部卒業、株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社。情報誌の流通や営業、編集のほか、ビジネスプランニングや「じゃらんnet」の大規模リニューアルに携わる。オンラインサービス「ホットペッパービューティー」の立ち上げでは事業部長として指揮を執る。2018年4月に株式会社リクルート代表取締役社長に就任し、2025年4月より現職。

学長補佐
(データサイエンス担当)
経営学部 経営学科 教授
新学環開設準備室室長
荒木 万寿夫
ARAKI Masuo
修士(経済学)(青山学院大学)。青山学院大学大学院経済学研究科経済学専攻博士後期課程標準年限満了退学。専門分野は経済統計学、情報教育。1999年青山学院大学経営学部経営学科専任講師に着任し、2010年同教授に就任。2020年経営学部教務主任を経て、2021年学長補佐に就任し、現在に至る。
1.AI時代の今、
なぜ統計学から
データサイエンスを学ぶのか
後発こそ最先端
北村氏(以下、北村):青山キャンパスに新たに理系の学士課程を設置されると聞いた時、単純に「どんな学びができるのだろう」と興味を抱きました。データサイエンス系の学びは全国に普及しつつある状況だと思いますが、このタイミングでなぜ統計データサイエンス学環の設置に踏み切ったのでしょうか。
荒木教授(以下、荒木):現在、多くの大学がデータサイエンス教育のプログラムを展開し、本学でも学部単位では導入が進んでいます。その中で、2027年4月に設置構想中の本学環が「後発」であることは自認しています。さらに昨今は生成AIが急速に普及し、簡単なプログラミングやデータ分析を肩代わりしてくれる時代です。人間がデータサイエンスを学ぶ意義は薄れたのではないか、という疑問も抱かれるでしょう。
北村:データサイエンスはツールとしての側面が強く、そのものの仕組みを学ぶことの意義は問われ始めているかもしれませんね。
荒木:しかし私は「生成AI時代にこそ、統計学を核にしたデータサイエンスが社会に必要」だと確信しています。生成AIは過去に誰かが書いたテキスト情報を学習し、文章生成や要約、分析などを支援してくれますが、生成AIの拠り所は「過去」の情報が中心です。一方で、データから問題解決に役立つ知見を抽出するデータサイエンスにおいては、「現在」の社会情勢を正確に捉え、「将来」に向けて自ら問いを立てる力が欠かせません。そこで重要になるのが統計学です。現実世界の現象を把握するために正確なデータを収集する力、何が結果を動かすのかを探る現象構造の解明、根拠を示して合意形成に導く説明責任――これらは統計学が担う中心的な役割であり、人間こそが担える領域です。そこで、現在構想している学環では、統計学の専門スキルを養うことをひとつのミッションとしています。実は、アメリカでは統計学部が独立しているのが一般的ですが、日本では「統計」を冠した学部(学環)は本学が初めてとなります。
北村:本質を突いた画期的な試みだと感じます。後発であることは一見遅れをとっているようですが、前例から学べるという大きな強みがあります。現在のAI時代にフィットしたカリキュラムは、学生にとって絶好の学びの場でしょう。加えて特徴的なのは「学環」というシステムだと感じましたが、どういった意図が込められているのですか。

理系の学びをコアに、
連係5学部の知見をプラスし、
解像度の高い教育を実現
荒木:ありがとうございます。本学環では、まずデータを読み解くために欠かせない数理の基礎や統計学を学び、機械学習や情報科学へと学びを広げて、データサイエンスで問題を解決するための実践力を身に付けます。ただしデータサイエンスは適用フィールドが極めて広いため、理系の専門的な知識のみならず多角的な視点が不可欠です。そこで既存5学部との連係がもたらす豊かな知見を生かし、専門性と実践力を兼ね備えたデータサイエンス人材を育成するのが本学環ならではの特長となります。
例えば「AIの法と倫理」や「生成AIと教育・メディア」といったテーマを取り上げた場合、専門外の教員が聞きかじった知識で話すのと専門家が語るのでは、解像度も迫力も明らかに異なります。研究に裏打ちされていなければ説得力はありません。学環という仕組みであれば、教育人間科学部、経済学部、法学部、経営学部、理工学部という5学部の教員による授業が可能です。当初は学部としてスタートすることも考えていましたが、データサイエンス教育の在り方を考えた上で学環にたどり着きました。
北村:技術的な側面だけでなく、現実に沿ったあらゆる学問を多面的に講じる、そういった教育が可能になるのですね。もしも自分の学生時代にこうした学びの場があれば、とても興奮していたと思います。

2.社会における
統計・データサイエンスの
実践
統計で作り出す「売れる表紙」
荒木:北村さんは本学の理工学部化学科をご卒業されましたが、在学当時は統計やデータサイエンスによく触れていたのでしょうか。
北村:統計学そのものを専門的に学んだわけではないのですが、私はさまざまな製品の進化には素材の進化が関係しているという化学的な知見に対する関心があり、青山学院大学理工学部に入学しました。無機化学に関する研究を行う研究室に所属し、卒業研究では銅のキレート錯体の特性をテーマに取り組んでいました。研究の中で数字に触れる機会が多かったのは間違いありません。また、エンジニアの父が、探求心から自宅で家電製品を分解して仕組みを楽しそうに分析する姿を見せたり、クリスマスに望遠鏡や顕微鏡を私にプレゼントして自然にサイエンスの世界に誘ってくれたため「なぜこれが起こっているのか」と物事を客観的に解き明かそうとする姿勢が自ずと身に付いていったのだと思います。
荒木:そうだったのですね。リクルートに入社後は、統計やデータをどのように活用されていましたか。
北村:ビジネスでは感覚がものを言う場面が多々ありますが、その直感の支えとなる事実をデータで証明したいと思ってきました。私が青山学院大学理工学部を卒業してリクルートに入社した1990年代後半は、Windows95が登場し、インターネットが一般的に普及し始めた頃です。世の中が少しずつITを使ってビジネスを推進していこうという時代にキャリアをスタートしました。
荒木:理系的な発想力が求められ始めた時代だったのですね。
北村:統計学がビジネスに生きた瞬間として印象的なのは、今から20年ほど前の旅行情報誌『じゃらん』編集部での経験です。当時リクルートが取り扱っていた情報の中で「旅行」は、生活に必須というものではありませんでした。そうしたサービスが売れる仕組みを考えられれば、どんなビジネスにも通用する武器を得られると思い、自ら編集部への異動を希望しました。
いざ異動してみると、実際の編集は極めて感覚的なものでした。編集会議で繰り広げられるのは「このタイトルなら売れる」「この表紙の写真は良い」といった議論。どれも個人の感覚に基づいており、時には作り手のエゴも含まれていたかもしれません。編集長が変わり、その課題を共有する中で共に取り組んだのは、どのような表紙が売れる、もしくは売れないのかを統計学的に導き出すことでした。パートナーとなる統計学を扱う会社と組み、過去10年分の表紙データを遡り、そこに盛り込まれている文字・写真や、雑誌が販売された時期の景気など約300項目に分解。それらをもとに、ベイジアンネットワーク*という統計学的手法で表紙デザインと売り上げの因果関係を導き出し、「表紙の色」「見出しのキーワード」を選択するだけで、その表紙が販売部数に貢献する度合いを予測できるシミュレーションを作り出しました。
*データの因果関係を分析する手法の1つで、因果関係の強さを、ある事象が起こった場合に他の事象が起こる確率である「条件付き確率」の大きさから判断し、多数の事象間の因果関係をグラフィカルに整理する方法。

クリエイティブに
データという根拠を示す
荒木:そのような先端的な試みが20年以上前に行われていたとは非常に驚きです。シミュレーションからはどのような発見があったのでしょうか。
北村:面白いことに、旅行情報誌なのに表紙に大きく「旅」という文字を入れると、売れる確率が約90%も下がるという結果が出たのです。その背景には「旅」という言葉を読者がどのように捉えているかの実態がひそんでいました。追加の認知調査の結果、首都圏の場合、普段使っている交通手段とは違うものを使い、200km以上移動することが読者にとっての「旅」の定義だと分かったのです。確かに、普段の会話で「今週末、旅に行こう」とは言わないですよね。このことから、東京から見た箱根や熱海は「お出かけ」に分類されると分かり、「旅」と「お出かけ」の使い分けの客観的な判断が可能になりました。
荒木:統計学的に雑誌の表紙を分析し、売れる表紙作りの意思決定に役立てられたという、まさにデータサイエンスの実践が20年前から行われていたのですね。
北村:当時を振り返っても、画期的な取り組みだったと自負しています。「良いもの、面白いものを作ろう」という編集者の熱意はそのままに、データに基づいて表現を工夫することで、市場に合った情報を届けることができた事例です。
荒木:リクルートでは、今やデータサイエンスは当たり前の存在になっているのでしょうか。
北村:そうですね。2012、13年頃からは当社のデータサイエンスを担うエンジニアの数が増えています。彼らは会社が持つ豊富なデータから、改善のヒントや新たなものを次々と生み出してくれています。「このサービスにこれを入れたら、これだけ数値が変わった!」というバタフライエフェクト(些細な変化が大きな結果に繋がる現象)のような発見が日々もたらされています。
荒木:あらゆるデータにアクセスできる環境は、データサイエンス人材にとっては最高の舞台ですね。統計データサイエンス学環は青山キャンパスで初の理系の学士課程となりますが、データサイエンス自体はもはや文理の枠を超えたリテラシーとして位置づけられています。こうしたスキルが実際に社会で期待され、必要とされていることが良く分かりました。また、お話いただいたビジネスでの実例は、まさに生きた教科書です。本学環でも、実務でデータ分析に携わるビジネスパーソンを招いて、成功談に偏らず、現場での失敗や制約を伺ったり、また、「統計データサイエンス演習」という授業では課題解決をケーススタディとして学びます。「AIのビジネス実装」という授業では、社会実装の先端事例の考察を通して、成功談のコレクションに留まらず、失敗から抽出される再現可能な判断と手順も学問として体系化し、その知見を教育にフィードバックしていきたいと考えています。

3.これから必要なのは
大学と企業を繋ぐ
「ブリッジ」の存在
研究・実践の場となる
新たなフィールド
荒木:北村さんのお話からは統計やデータサイエンスが社会を動かすという期待を感じましたが、教育現場においては「生のデータ」を入手することの難しさがあります。研究材料として企業のデータを分析できることが最良である一方、データは企業にとっての戦略資産ですから、容易にご提供いただけるものでもありません。そこで私たちは、青山キャンパスを拠点にした「統計データサイエンス研究教育センター」を設置予定です。本センターがハブとなり企業と共同研究を展開し、そこに学生も参加して現場体験できる仕組みを作りたいと思います。幸い、青山キャンパスは「BIT VALLEY渋谷・青山」に存在するという地の利があります。企業や地域社会との共同研究は、学生にとって現場での学びを経験できる貴重な機会になるうえ、学習や研究を後押しする強い動機づけにもなるでしょう。
データサイエンス人材の育成においては、そのステップアップフローを「見習い」「一本立ち」「棟梁」といった職人になぞらえて表現されるように、どこか「師匠の背中を見て学ぶ」側面があります。なぜこの変数をこの形に加工をしたのか、なぜここから分析を始めたのかと、先輩研究者の仕草を間近で見て暗黙知を得る意義は大きいのです。企業側から見て、こういった共同研究の場はどのように映りますか。
北村:企業にとっても大学の専門知には大きな魅力があります。ただ、二者のマッチングを進めるためには一工夫が必要だろうというのが率直な感想です。あくまでも大学は研究教育の場であるため、何ができるのか、どのようにビジネスに生かせるのか、企業にとってプランニングしづらい側面があります。研究とビジネスの間の谷間を埋める橋渡し的な存在が必要になってくるでしょう。
荒木:継続的に企業と連携していくためには、教育のために協力していただくのではなく、実りある研究成果を持ち帰ってもらう必要があることは痛感しています。お互いに利のある関係を作るために、同じ関心や価値観を持っているかどうかの見極めが課題ですね。
北村:そうですね。そのためには大学側が取り組んでいる「問い」を提示するのが一つの手かもしれません。「この問いに対して、一緒に答えを出してくれるパートナーを探しています」とはっきり明示されていると、同じ課題を見ている企業としてはアプローチしやすくなります。
荒木:なるほど。
北村:現在の日本のビジネス界は、次々と既存の枠組みが壊され、急速に変化しています。つまり、次の一手を見つけるために、データや統計、あるいはテクノロジーを駆使して現状を分析する取り組みがこれまで以上に求められているのです。そういった意味で、統計データサイエンス学環での教育・研究を通して、そこで学ぶ学生の皆さんが、次世代を作る人材として活躍されることと思います。
荒木:お話を伺って、ビジネス界における統計学やデータサイエンスへのニーズの高さを実感できました。カリキュラムと研究組織の両軸で、専門性と実践力を備えたデータサイエンス人材の育成に取り組みたいと思います。また、「統計データサイエンス研究教育センター」を基盤に、地域の企業や行政からご相談を受けた実課題や問題意識を本学環で共有し、また、学環の教育プログラムをビジネスパーソンのリスキリングにも展開するなど、大学とビジネス界の対話と交流を広げられればと思います。大学の知と人材を現場の課題解決に接続し、得られた知見を教育や研究へ還元することで、相互に価値を高められる好循環が生み出せれば理想的だと思います。
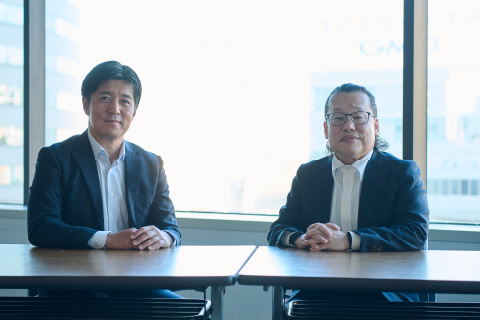
- 【後編】
-
統計データサイエンスの
思考力を片手に、
好奇心で未来を切り拓く不確実な時代に求められる
「統計マインド」とは?
そして、青学が育む
「サーバント・リーダー」像に迫る。
