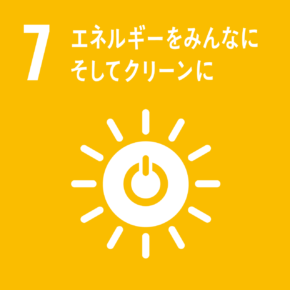- MENU -
POSTED
2025.10.23
TITLE
AGU環境学シンポジウム「バイオリージョナリズム(生命地域主義)を手がかりに水、環境と開発を考える―環境をめぐる人文科学・社会科学・自然科学の対話―」を開催
2025年7月12日(土)13~17時に、大学14号館 第18会議室にて、AGU環境学シンポジウム「バイオリージョナリズム(生命地域主義)を手がかりに水、環境と開発を考える―環境をめぐる人文科学・社会科学・自然科学の対話―」を開催しました。
人間は、言語による認識を基礎に〈環境〉を積極的に改変する特異な生物です。18世紀後半に起こった産業革命以降、人間による〈環境〉の改変は加速度的に進み、気候変動、生物多様性喪失などの深刻な環境危機を引き起こしています。これを乗り越えるためには、あらゆる知識を結集して、人間と〈環境〉の関係を再構築することが必須です。そのために、総合大学である本学で、人文・社会・自然科学の各分野で独創的な環境研究を進めている研究者が集い、研究成果を共有する機会として「AGU環境学シンポジウム」が企画されました。
異分野の研究者同士が会話をするためには、“共通言語”が必要です。このシンポジウムでは、EVANOFF名誉教授(元国際政治経済学部)のバイオリージョナリズムBioregionalism(生命地域主義)の思想を“共通言語”としました。1970年代のアメリ合衆国に始まるバイオリージョナリズムは、今日、日本を含む世界各地でその実践が進められています。人間と〈環境〉の関係を再構築するための重要な鍵の一つです。EVANOFF名誉教授の論文によれば、バイオリージョナリズムは、行政区分ではなく、川などの地形に沿った〈地域(bioregion, life-place)〉の中で、食、衣料、家(shelter)、エネルギーなど、人間に必要なものに関する資源循環型社会を実現しようとする思想です。ただし、〈地域〉の中に閉じこもるのではなく、“地球規模で考え、〈地域〉で行動する”(the Green slogan)の立場にたち、異なるコミュニティ間の対話を通して新しい規範を定めていきます。
 内田達也副学長
内田達也副学長 開会挨拶
シンポジウムの冒頭で、内田達也副学長(広報及び国際連携担当)<国際化推進機構長、国際政治経済学部国際経済学科教授>から、「地球規模での大学連携と共同研究の推進と主導」という中期目標達成のための一つとして、このAGU環境学シンポジウムを位置づけたい、との開会のことばがありました。
 内田達也副学長
内田達也副学長  EVANOFF名誉教授
EVANOFF名誉教授 基調講演「バイオリージョナリズムとグローバル倫理」
次に、EVANOFF名誉教授の基調講演「バイオリージョナリズムとグローバル倫理」が行われ、EVANOFF名誉教授は、〈地域〉の自然と文化を感じ取りながら、〈地域〉を自分の生きる場所として「再定住rehabit」することの重要性と、バイオリージョナリズムを通して、地球規模の課題に応えてゆく広い視野big pictureを持つことの大切さを訴えました。〈地域〉に根ざした“小さな物語”をいかに地球規模の“大きな物語”につなぐか。このシンポジウムのテーマが見定められました。
 EVANOFF名誉教授
EVANOFF名誉教授 続くセッションでは、⑴「〈地域〉における水」、⑵「〈地域〉の視点からの環境と開発再考」という二つのトピックについて、それぞれ4人の研究者から報告が行われました。
セッション1:〈地域〉における水
行政は川を分断します。しかし、バイオリージョナリズムでは川の「流域」という単位が重要となり、さらに「流域」を含めた水循環が問題となります。⑴の報告は以下のとおり。
音風景で辿る土地の記憶と感性(鳥越けい子名誉教授〈元総合文化政策学部〉)
鳥越名誉教授(サウンドスケープ研究)は、「水」を地理と気候が調律する地球の基調音と捉えた上で、池を水源として川がつないできた江戸という〈地域〉の音の文化が近代に破壊されてきたことに警鐘を鳴らしました。
水のネイチャーライティングとBlue Humanities(結城正美・文学部英米文学科教授)
結城教授(アメリカ文学・エコクリティシズム)は、境界を壊すという「水」の性質に注目するBlue Humanitiesを紹介。また、文学でしか語りえない、自然に関する物語があることの重要性を強調しました。
地域環境要因としての水(三條和博・経済学部教授)
三條教授(地球科学・地理学)は、流域を単位に水循環を考える合理性を説き、今日の河川法における「環境用水」意識の高まりを示しつつ、流域内における「水の地産地消」(反復利用)の必要性を提言しました。
古代都市・平城京の水環境(小松靖彦・文学部日本文学科教授)
小松教授(日本文学)は、萬葉歌人が、平城京の主要河川・佐保川の水質管理によって実現した清浄な水景観を好んだ一方で、下水には無関心であったことを解説し、都市において水循環を意識することの難しさを指摘しました。
-
鳥越けい子名誉教授
-
結城正美・文学部英米文学科教授
-
三條和博・経済学部教授
-
小松靖彦・文学部日本文学科教授
セッション2:〈地域〉の視点からの環境と開発再考
バイオリージョナリズムはグローバリズムの推進する大規模開発に疑問を呈します。環境保全と開発のバランスの再考もバイオリージョナリズムの課題です。⑵の報告は以下のとおり。
取り残された地域にとってのSDGs、グローバルバリューチェーン(堀江正伸・地球社会共生学部地球社会共生学科教授)
堀江教授(国際協力論、非伝統的安全保障論、インドネシア地域研究)は、西ティモールでは灌漑用水路建設に慣習法が有効に機能する一方で、政府の効率優先の農業政策が格差拡大を招いており、既存の社会制度の役割を見直す必要性を説きました。
国際協力事業評価の再考―給水案件を中心に(島村靖治・国際政治経済学部国際経済学科教授)
島村教授(開発経済学、応用計量経済学)は、ザンビア、ミャンマーなどの例から、水に関する国際協力事業をより効果的にするためには、下水道も含めた水循環と、〈地域〉に即した運営主体が不可欠と訴えました。
太陽光発電の最新技術と廃棄問題への取り組み(石河泰明・理工学部電気電子工学科教授)
石河教授(半導体工学、データサイエンス、太陽光発電技術)は、エネルギーの地産地消を強力に促進する建材一体型太陽光発電や、性能低下の太陽光パネルのアップサイクルが有する大きなポテンシャルを示しました。
資源はめぐる、地域はつながる―都市鉱山から広がる地域資源循環の可能性(南部和香・社会情報学部社会情報学科教授)
南部教授(環境経済学、計量経済学)は、電子機器に内臓されたレアメタルが相当量に上る事実を指摘。また、若い人々の「再定住」のきっかけともなる、地域環境資源とのつながりを体験する環境ワークショップを紹介しました。
両セッションから、〈地域〉をつなぐ「水」の性質と、〈地域〉における資源循環の未来像が浮かび上がってきました。
-
堀江正伸・地球社会共生学部地球社会共生学科教授
-
石河泰明・理工学部電気電子工学科教授
-
南部和香・社会情報学部社会情報学科教授
※セッション2にご登壇いただいた島村教授のお写真は、記録の不備のため掲載が叶いませんでした。
ディスカッションでは、環境ワークショップの“楽しさ”とは何か、建材一体型太陽光発電の開発途上国での利用の可能性は、などについて領域を超えた意見交換が行われました。最後に、黄晋二理工学部長(国際化推進機構会議構成員、理工学部電気電子工学科教授)から、さまざまな分野の環境研究の交錯に驚き覚え、この分野横断の研究を国際共同研究拠点の構築につなげてゆきたい、という閉会のことばがあり、シンポジウムは幕を閉じました。
-
ディスカッションの様子①
-
ディスカッションの様子➁
-
黄晋二理工学部長
学内外から環境に関心のある人々が参加し、シンポジウム終了後も講師に熱心に質問する姿があちこちで見られました。