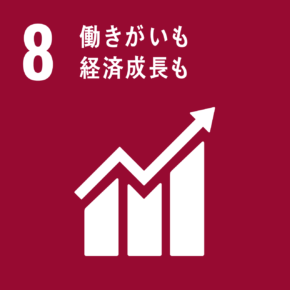- ホーム
- 研究機関・研究者の皆様へ
- 【理工学部】理工学部60周年記念事業 Ronald Vale博士 講演会「AIが生命科学研究と教育に与えるインパクト(Impact of AI on Biology Research and Education)」を開催
NEWS
- MENU -
POSTED
2025.11.06
TITLE
【理工学部】理工学部60周年記念事業 Ronald Vale博士 講演会「AIが生命科学研究と教育に与えるインパクト(Impact of AI on Biology Research and Education)」を開催
分子モータータンパク質キネシンの発見者であり、細胞生物学・分子生物学の分野で目覚ましい研究成果をあげてこられたロナルド・ベール博士(米国・Janelia Research Campus)を、2025年10月末より理工学部の招聘教授としてお迎えしました。この機会を捉え、2025年10月30日(木)に、青山キャンパスの本多記念国際会議場にて、理工学部創設60周年記念事業「AIが生命科学研究と教育に与えるインパクト」と題した講演会を、本学および学外の大学院生、教員、研究者を対象に開催しました。
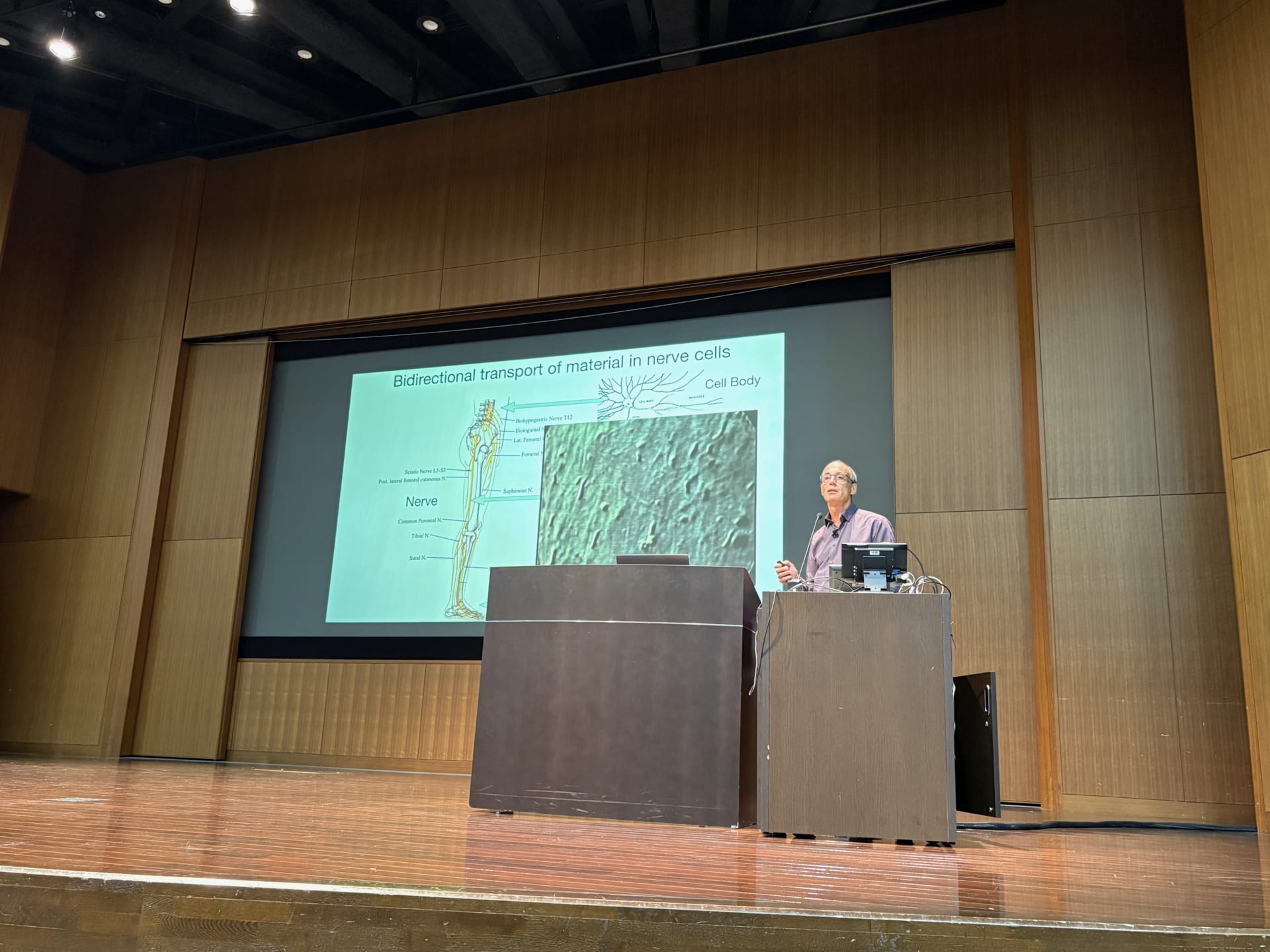
ロナルド・ベール博士の講演
講演会では、ベール博士はAIを活用して新たな発見につながった具体的な例として、「分子モータータンパク質による輸送制御」の研究について紹介しました。細胞内輸送に関わる分子モーターには、キネシンとダイニンという互いに逆向きに移動するタンパク質が存在します。それぞれの運動の仕組みについては理解が進んできましたが、逆向きに動く2つの分子モーターが、細胞内で荷物をどちらの向きに移動させるのかという制御の詳しい仕組みは分かっていませんでした。ベール博士はミトコンドリアの輸送に着目し、ミトコンドリアにキネシンやダイニンを結合させるアダプタータンパク質TRAKが輸送制御に関わっているのではないかと考えました。そこで、AIベースの構造予測ツールであるAlphaFold2を用いて、TRAKタンパク質の構造を推定し、推定された構造を元に仮説を立て、それを実験的に検証するというアプローチで、全く新しい輸送制御の仕組みを明らかにしました。ベール博士はその過程で、どのような考えで最適なアプローチを選択し、予想外の結果になったときにどのように対処したのかなど、具体的なエピソードを紹介しました。またベール博士は、AIを使った構造予測ツールを誰でも簡単に活用できるようになった今、AIを活用することで研究の可能性が広がり、それを活用するために構造分析の知識は不可欠なものになると強調していました。
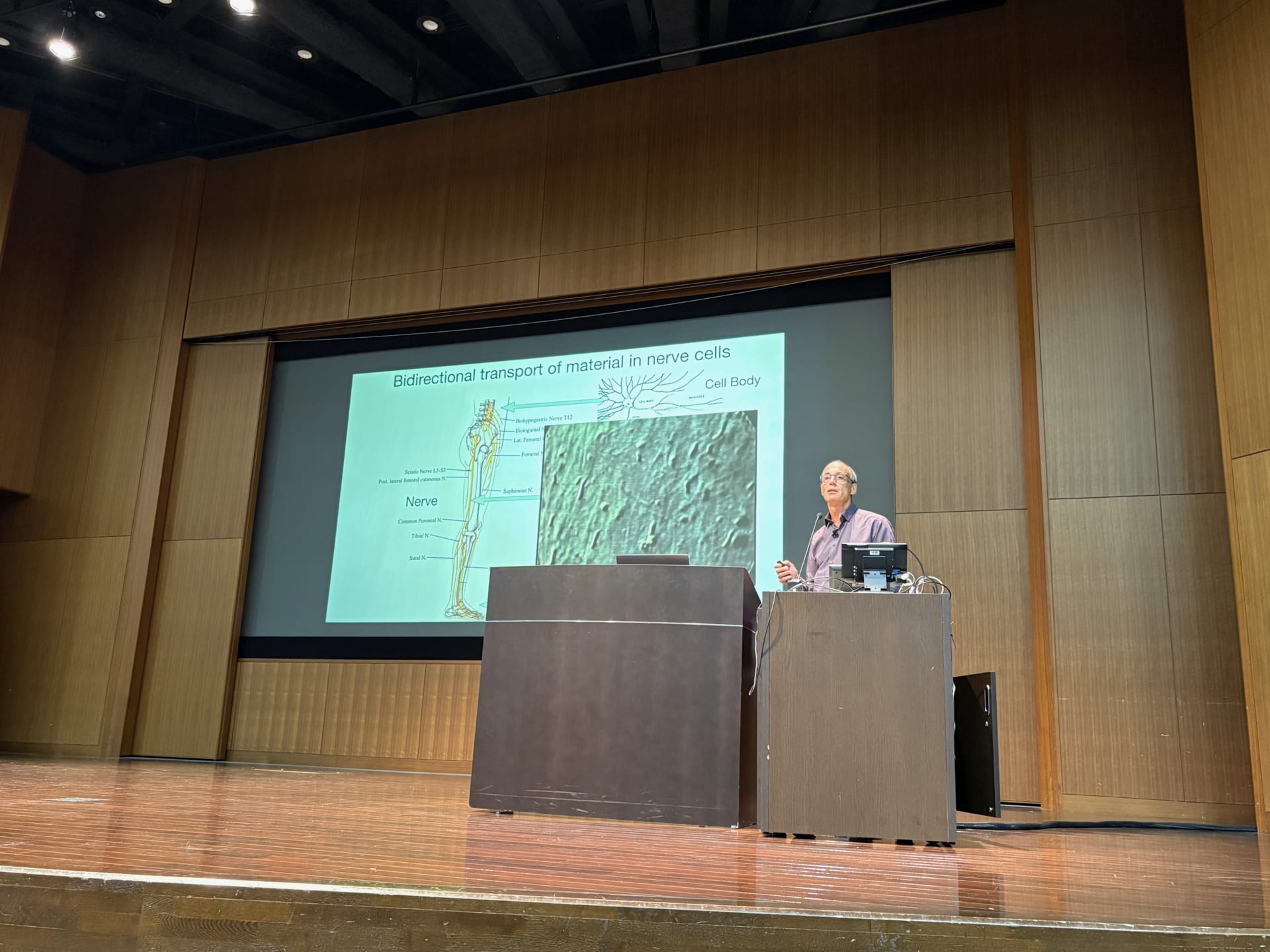

ベール博士は生物学教育の面でも多大な貢献をしており、講演の最後にはベール博士が立ち上げたいくつかのコンテンツについて紹介しました。最先端の研究者が自身の分野を解説する動画を集めたiBiology、生物学の重要な発見に至る経緯を発見者本人が豊富な画像を使って解説するXBioなど、生物学の最先端の成果に気軽にアクセスできるプラットフォームの立ち上げに尽力してきました。
その後、参加された内外の教員や大学院生から多数の質問が寄せられ、ベール博士は一つ一つ丁寧に答えていました。質疑応答の最後には若手研究者に向けたメッセージを述べ、1時間半の講演会が終了しました。なお、講演会終了後、大学院生や若手研究者がベール博士と話をするために長い列をなし、さらに1時間半ほど懇談が続きました。